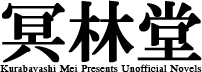本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
家来と王様
[2] 俺の日常
■ ■ ■
空が、広い。フェンスに背中を凭れて座っていると、心地いい風が前髪をふわふわと撫でていく。
俺は、ここにいるのがとても好きだ。校庭や窓の開いた廊下から流れてくる他の生徒たちのざわめきを聞いているのも楽しいものだ。
北校舎の屋上は、もともと運動部の三年男子が取り仕切っていて、俺たちの代にもそれが引き継がれてきた。昼休みの陣地取りなんてバカバカしいことだとは思うけど、気楽に休息できるのはありがたい。
権力争いも、遠い昔の先輩たちの出来事で、俺にはさして関係ない。とは、言い切れないのかもしれない。ドアのあたりが騒がしくて、俺はそっと目を開けた。
「お前、一年だろ。こんなトコ来ていいと思ってるのかよ」
坊主頭の連中が、ドア枠に手をかけて踊り場の方を見下ろしていた。その向こうにいるのはきっと、影山なのだろう。普通の一年だったなら、ここには決して近づかない。
だけど、あいつをここに呼びつけたのは俺だ。助けてやるべきなのだろうが、俺は、もう少しこの爽やかな風を感じていたかった。
「どいてもらないですか」
「人の話聞いてんのかよ」
「俺、そっちに行く用事あるんで」
あーあ、と、俺はため息をつきたくなった。そんな言い方をしたら、相手を余計に苛立たせるに決まってる。
少なくとも、俺はそうだ。そして、入口近くでたむろしている野球部員たちも同じらしい。
なんだこいつ、とか、生意気だ、とか、つまらない台詞が聞こえる。これじゃあ、せっかくの日向ぼっこが台無しだ。
仕方がない、迎えに行ってやるか。俺が重い腰を浮かす気になった頃、向こうの方で聞き慣れた声が聞こえた。
「なにやってんだ、影山」
「岩泉さん」
俺が出るまでもなさそうだ。俺は体をゆっくり伸ばして、もう一度目を閉じた。
瞼を閉じていても、空の青さが俺の目にはよく見える。きらきらと輝く太陽の温かさも、気持ち良い風の爽やかさも。
騒がしかった屋上に、久しぶりに一年生が足を踏み入れたらしい。こっちへ近づいてくる足音が聞こえて、俺は口元を緩ませながらゆっくりと息をついた。
「呼んだなら、ちゃんと面倒見てやれよ」
「でも、問題なかったんでショ」
この野郎、と、岩ちゃんの顔が言っていた。その隣で、飛雄が俺に向かって両手を差し出した。
「お待たせしました」
「わー、ありがとう」
棒読みで、俺は言った。飛雄の手に握られていたパックは汗をかいていた。
購買の隣にある自販機でしか、ぐんぐんヨーグルトは売ってない。昼間にこれを持ってくるよう、朝の内に言っておいたのだ。
「じゃ、俺戻ります」
「え、お前食ってかねぇの?」
俺の隣に腰掛けながら、岩ちゃんが驚いたような顔をする。周りはチラチラと俺たちのことを見ていたけれど、影山は別に気にしていないようだった。
「ソレ買ってこいって言われただけだったんで」
平然とした顔で、影山は言った。お前、もう少し言い方ってのがあるんじゃないのか。いやでも、こいつが空気を読めないことは端からわかっていたことだ。
それを聞いた岩ちゃんは、どういうことだ、と、俺を横目で睨みつけていた。影山は小首を傾げて、俺が次に発言するのを待っている。
「うん。もう帰っていいよ」
「ウス。失礼しアす!」
大きな声を屋上の上に響かせて、影山は深く頭を下げた。そのまま小走りに駆け出そうとする影山に、俺は慌てて声をかける。
「あ、これ。一個あげる」
影山はうまいこと、俺が投げた紙パックを受け取った。俺はもともと、そのつもりだったのだ。こんな甘いの、二つも飲めるわけがない。
「お駄賃だよ」
ひらひらと掌を振ると、影山はペコリと頭を下げて、そのまま再び走りだした。俺は笑顔で送り出して、パックの背中に刺さっていたストローを取り出した。
プス、と、それを刺したところで、パックが岩ちゃんに取り上げられる。あ、と、俺は声を洩らした。恐る恐るそっちを見ると、岩ちゃんは目を細め、眉を難しく寄せたまま、俺の方を睨みつけていた。
ストローをガジリと噛んで、俺の発言を待っている。沈黙に耐え続けられるはずもなく、俺は苦笑して頭をかいた。
「いやぁ、なんかさぁ…、なんでもするからサーブ教えて下さいって言われたから」
「だからって、パシリに使ってんじゃねーよ」
「だってなんか命令しないと、あいつすごい顔して睨んでくるんだもん」
この状況を影山のせいにして、俺は母さんの用意してくれた包みを解いて、弁当箱を開けた。
別に嘘はついてない、半分は。言っていないことがあるだけだ、無論、俺からそれを言うつもりはない。
「まさか、今朝のアレもそのせいか」
気がついて、岩ちゃんはストローを口から放した。さすがは幼なじみ殿。察しが良い、と、俺は思った。
隠すつもりはなかったけれど、自分から言うことじゃない。取引を持ちだしたのが俺なのだという事実は、岩ちゃんにはあまり知られたくないと思った。
「『可愛がってやれ』っていうから、俺なりにやってみようと思って」
岩ちゃんは、ちゃんと部長職をこなしている。影山への態度について、俺はいつも小言を言われた。
今朝は珍しく、俺は影山と二人で朝練のためのネットを張った。そうしている内やってきた岩ちゃんの驚いた顔は痛快だった。
「ちゃんと教えてやるんだろうな」
購買で買ったパンを取り出しながら、岩ちゃんは釘を刺してくる。
「一応は」
そう答えた俺の足が岩ちゃんに蹴飛ばされた。いて、と声をあげた拍子に食べようとした唐揚げが箸からこぼれる。
「大丈夫だよ、ちゃんと約束は守るから」
弁当箱でなんとかそれを受け止めて、俺は苦笑しながら言った。焼きそばパンを頬張りながら、岩ちゃんがフェンスにもたれる。
「まあ別に、いいけどよ」
幼なじみというものは、都合がいいし、悪くもある。わざわざ言葉にしないでもわかってくれるのは楽っちゃ楽だ。だけど、知られたくないことまで知られてしまうのは厄介だ。
「部員同士で仲良くするのは悪くない。いい刺激になるかもしれないしな」
それは、影山にとってのことを言っているのか、俺にとってのことなのか──。俺は、わざわざ聞こうとしなかった。聞かなくても、きっと岩ちゃんの言いたいことがわかったから。
「だけど、あんまりイジめるなよ」
「ひっどいなぁ。俺が後輩イジめたことなんてあったっけ?」
もう一度、岩ちゃんが俺を睨みつけた。もう一度蹴られないように、俺は急いで弁当箱の残りを口に放り込んだ。
本当に、いい天気だ。洗いたての布団に寝転び昼寝をしたくなってくる。
両足を前に伸ばして、ごちそうさまを言いながら気持ちの良い息をつく。軽く喉が乾いていたから、俺は鞄に片手を突っ込み、ガサゴソと中を探った。
はぁ、とため息をついて、岩ちゃんがストローを吸う。ズズ、と音を立てて、紙パックがべこりと凹んだ。
「思ったより甘ェな、コレ。お前、こんなの好きだったけか?」
空になったパックを潰しながら、岩ちゃんが言った。朝の内に買っておいたミネラルウオーターを取り出して、俺は、にっこり笑みを作った。
「え?」
幼なじみというのは、やっぱり都合がいいものだ。俺がなにも言わなくても、俺が言いたかったことの意味を岩ちゃんはわかってくれる。
影山の才能は眩いほどだ。そこに技術と体格が備わったなら、うちのチームのレベルはまた一段レベルを上げることとなる。
その場に軽く寝転んで、膝を重ねて足を組んだ。
「じゃあ俺、予鈴まで昼寝するから」
俺たちのいつもの、昼休み。柔らかい布団とは違うけれど、隣に岩ちゃんがいるからか、このまま目を閉じればきっと気持ちいいだろうと俺は思った。
「起こさねーぞ」
「えー、意地悪」
そう言って苦笑したけど、本気にしているわけじゃない。岩ちゃんがちゃんと起こしてくれると、知っているし、信じている。
本格的に寝るわけじゃないが、休息は必要だ。午後イチは退屈な数学だったし、その後は部活がある。
岩ちゃんが食事を摂るのを聞きながら、ゆっくり過ごす特別な時間。俺はまだ、こんな平穏な日常がこれからもずっと続くと、都合よくも信じていたし、疑っていなかった。
■ ■ ■
「えー、今日もなの?」
靴紐を結んだ手を止めて、俺は言った。他の部員たちがいなくなって、部室には俺と岩ちゃんの二人だけだった。
監督とのミーティングが終わった岩ちゃんを、俺は待ち受けていた。昨日と違って、今日こそは一緒に帰ろうと思っていたから。
「悪いけど、しばらく一人で帰ってくれ」
制服の襟を正しながら、岩ちゃんは言った。ロッカーの扉の内側の、小さな鏡を見つめながら。
茶化しちゃいけない雰囲気を、俺は即座に感じ取った。昼間も、部活の最中もいつもと変わらなかったから、『普段と違う』ということに気づくのが遅れてしまった。
「なにかあった?」
気にしてない風を装いながら、俺は尋ねた。顔は挙げなかったけれど、俺は岩ちゃんの気配を探ろうと体の左側に神経を集中させていた。
「…泉の伯父さんが、入院してるんだ」
「え、義弘伯父さん?」
俺は驚いて、思わず顔を上げてしまった。ゆっくりと頷いて、岩ちゃんが座る俺を見下ろした。
義弘伯父さんは岩ちゃんの親戚で、仙台の別の地区に住んでいる。子供が男の子じゃなかったからか、小さい頃は、俺もよく遊んでもらった。
デパートの屋上に連れてってくれたこともある。どこか怪我でもしたのだろうか。俺が聞きたかったことを、岩ちゃんは教えてくれた。
「癌が見つかって、もう末期なんだって」
体が、一瞬で凍りついたような気がした。そうしてだんだん、体の力が抜けていく。存在を知ってはいたけど、経験したことのなかった絶望が、俺の呼吸を奪っていった。
「末期って、どういうこと?」
震える口唇で、俺は尋ねた。俺の方を向いたまま、岩ちゃんは視線を逸らしていた。
俺の顔が引き攣ってるのをわかっていて、遠慮、してくれていたのかもしれない。
「もう、帰ってこれないってことだ」
俺たちは、まだ十五だ。人はいつか死ぬのだと、知ってはいたけど覚悟なんてできちゃいない。
いや、岩ちゃんは、できているのかもしれなかった。ベンチの上で横にずれて、俺は岩ちゃんに、座るように促した。
「ママさん、どうしてる?」
きっと、岩ちゃんはこれからどこかに行かなきゃいけないのだ。足止めをするのは気が引けたけれど、俺と二人でいるときくらい、少しは気を休めてほしい。
「流石に、凹んでる。毎日お見舞いにいって、伯母さんちの手伝いもしてるからな」
ジャージ姿の俺の隣に、制服に着替えた岩ちゃんが腰を下ろす。後ろ手に体重をかけて、ふう、と息を吐き出しながら。
「こっちにいる親戚、うちだけだからな。」
岩ちゃんの祖父母は、片方は別の親戚と暮らしていて、もう片方が岩ちゃんと同居している。義弘伯父さんは岩ちゃんの母方の親戚だ。
いつも親切にしてくれるママさんが胸を痛めているのだと思うと、俺の気持ちまで締め付けられてくるような気がしていた。それよりなにより、隣に座る幼なじみの心中が気がかりだった。
「そういうわけだから、帰りはこのまま病院寄るわ。いつになるかわかんねぇけど、いきなり部活出れなくなるとかもあると思う」
監督にはさっき言った、と、岩ちゃんは付け足した。岩ちゃんがあんまり冷静に言うものだから、俺はなんだかムズムズして、聞かずにおれなくなってしまった。
「大丈夫?」
聞き方を間違えた、とは、自分でもわかっていた。けれど、どう言えばいいのか俺にはわからなかった。
岩ちゃんが俺の方を向いて、驚いたように目を瞠る。だんだん顔が緩まって、綻ぶように微笑んだ。
「俺より、周りが凹んでるから。俺が落ち込むわけいかねぇだろ」
俺の肩に叩くように手を置いて、岩ちゃんは立ち上がった。もう、行かなきゃいけないらしい。いてもたってもいられなくて、俺は急いで立ち上がり、思わず口を滑らせていた。
「ねぇ、キスしようよ」
どうしてそんなことを言ったのか、自分でも驚いた。けど、理由はあとからついてきた。
俺はきっと、岩ちゃんを慰めてやりたかったのだ。だけど、たかが幼なじみである俺にできることは限られている。俺にしかできないことは、それくらいしかなかったのだ。
「はぁ?」
岩ちゃんは足を止めて、呆れたような口ぶりで俺の方へと振り返った。俺は目を閉じて、顎を突き出した。いつもどおり、装いながら。
「いいじゃない。久しぶりに」
キスをするのは、初めてじゃない。俺たちはもうだいぶ長い付き合いで、キスもセックスも経験済みだ。
もちろん、それが普通でないことはわかっている。だから周りに言う気はないし、知られようとも思っていない。
だけど、そうする時にどれだけ気持ちいいかをわかっているから、そうすることで岩ちゃんが少しでも楽になれたら、それでいいと思っていた。
目を閉じていた俺の頬に、ふわ、と、やらかいものが触れた。俺の睫毛がぴくりと動く。優しい温もりが離れてしまうのが嫌で、俺はしばらく身動きできないでいた。
「ほら、行くぞ」
岩ちゃんが足を退いて、扉に向かって歩き始めた。俺は、す、と目を開いた。ほんの少しだけ、胸がちくりと痛むのを感じながら。
どうして、頬だったんだろう。別に、口唇だってよかったのに。
だけど、痛みはほんの一瞬だった。岩ちゃんの顔が少し赤くなったのを見つけたから、拗ねた気持ちは和らいで、俺は素直に手を差し伸べた。
「鍵、俺が預かっとくよ」
岩ちゃんは、意外そうな顔をした。帰らないのか、とも聞きたそうだが、俺は一度伸ばした腕を引っ込めようとはしなかった。
「先行っていいよ。大丈夫、俺もすぐに帰るから」
これ以上引き止めても、相手に迷惑をかけるだけだ。もうしばらくの間なら、平静を装っていられるだろう。
ニコニコと笑う俺の右手に、チャリ、と、鍵が落ちてきた。年季の入った鍵を託して、岩ちゃんは部室のドアを開けた。
「寄り道すんなよ」
「しないよ」
ひらひらと手を振って、俺は笑顔で岩ちゃんを見送った。岩ちゃんがちゃんと出ていけるように、罪悪感を残していかないように。
どうして、あんなことを言ってしまったんだろう。片頬が喜んでいる一方で、口唇が切なさを覚えている。
そこを、きゅ、と噛み締めて、俺は携帯を取り出した。随分遅くなってしまった、けれど、まだ間に合うだろう。
期待外れと感じてしまうくらいなら、あんなことを言わなきゃよかった。唐突な告白で頭もうまく回っていない。
胸のもやもやをさっさと払拭したくって、俺は携帯のロックを解いた。俺の親指と人差し指は、いとも容易に一人の後輩の連絡先を探しだした。