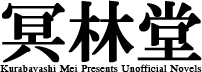本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
家来と王様
[1] 契約成立
あの日、俺は飛雄をどうしたかったのだろう。殴るつもりだったのか、突き飛ばすつもりだったのか──。岩ちゃんが止めてくれなかったら、俺は飛雄をどうしただろう。
『もしも』の話なんて、考えても仕方がない。あの時の俺は、自分でも照れくさくなるくらい、切羽詰まっていたと思う。
だけど俺には岩ちゃんがいて、信じている仲間がいた。飛雄は相変わらずの無邪気さと残酷さで、俺を追っかけ回して来ていたけれど。
「及川さん、サーブトスのコツを教えて下さい」
部活が終わって、みんなと別れた帰り道。長い昼の時間が終わり、夜が始まったばかりだというのに、電灯には虫達が吸い寄せられるように集まってきていていた。
「ヤだよ、バーカ」
もう、『バカなの?』と聞くことも、『バカでショ』と呆れることもやめた。コイツは本当にバカなのだから、構っていてもしょうがない。
「聞いてなかった? さっき言ったでショ、『解散』って」
いつもなら岩ちゃんと二人で帰るのだけれど、今日は先に帰られてしまった。家の用事で、どこかに寄るのだと言っていた。
俺が飛雄を避けるため、わざと岩ちゃんとの時間を作り続けていたことを彼は重々承知している。いい加減一人で帰れ、なんて、つれない幼なじみじゃないか。
「今日じゃなくて、明日でも」
練習が終わって、飛雄はいつものように俺を探して追いかけてきた。岩ちゃんがいれば、上級生だけの空気をつくって飛雄を追い出してしまえたのに。
「昨日もヤだ、今日もヤだって言ったのに、どうして明日は大丈夫って思えるのかな」
飛雄に見つかる前に、さっさと帰ろうと思っていた。だけど飛雄は、やっぱり俺を見つけてきた。はぁ、と深くため息をついても、飛雄はまったく動じない。
「じゃあ、明後日は?」
いい加減、空気を読んでほしいものだ。この掛け合いは、もう何ヶ月も前から続いている。
「イヤです」
「その次なら」
「練習試合入ってるでショ」
「夕方は空いてるじゃないですか」
「お前ねぇ、お疲れの先輩をこき使おうっていうの?」
俺はできるだけ、早足で歩いているはずだった。それに少し遅れて、駆け足で飛雄がついてくる。
俺より小さいくせに、歩幅も狭いくせに。俺に遅れないように、必死に、懸命に。
「…また明日、頼んでみます」
眉をひん曲げて、口唇をとんがらせて、飛雄は言った。ちら、とそれを見下ろして、俺は思わずため息をついた。
時々、考えることがある。コイツが俺の後輩でよかった、同学年でなくてよかった、と。
もし飛雄が俺と同い年だったら、俺はどうなっていただろう。コイツが二個下だから、俺が二個上だから、最低限『先輩』らしく振る舞っていられるのだ。
そう考えると少し安心するけれど、飛雄が俺を脅かしていることに変わりはない。やはり、いけ好かない奴だ。こんなに俺をこんなに身近で、揺さぶりかけてくるなんて。
「明日も、絶対断るけどね」
「明日になったら、気が変わるかもしれないじゃないですか」
飛雄が入部してきてから、もう何ヶ月経っただろう。俺はそんな長い間、ずっとコイツに追い掛け回されている。
飛雄が女の子だったなら、少しは楽しんでいられたろうか。いや、いくら女の子でも、こんなブサイクでムカつく奴はお断りだ。
ムカつく、生意気で、可愛くない後輩。なんだ、イイトコ無しだな。かといって、俺にはこいつを突き放すこともできない。
「悔しかったら、自分でなんとかすればいいじゃん。俺のことなんかほっといて、この間に練習でもなんでもしてればいいのに」
後輩だから? 岩ちゃんに怒られるから?
──俺は多分、こいつを羨んでいるのと、妬ましいと思うのと同様に、それと同じだけ危うんでいるんだと思う。
こいつの力を、誰かになにかに食い潰させたくはない。こいつをすごいと、恐ろしいと思うと同時、俺はきっと、こいつがもっとすごくなるのを期待していた。
「でも、岩泉さんが」
顔を上げると、夕闇を吸い込んだ空はすっかり暗く、星がちらちらと輝き始めていた。今日の夕飯はなんだろう。なんとなく、カレーを大皿でかっ食らいたいと思っていた俺は、飛雄の思いがけない発言に、足を止めた。
なに、それ。どうしてソコで岩ちゃんが出てくるの?
飛雄を見下ろす俺は、どんな顔をしていただろう。ああもう、やだやだ。どうしてこいつは無意識に俺をかき乱してくるのだろう。
「仲間(チームメイト)なんだから、聞いたら教えてくれるはずだって」
飛雄はいつもの、まっすぐな瞳で俺を見つめていた。もう夜だというのに、電灯や星の光まで吸いこんで、ギラギラと輝くような眩いほどの双眸で。
なぜか、俺はホッとした。すぅ、と力が抜けていって、次の瞬間、俺は腹の底が煮えたぎるような、どうしようもない苛立ちに襲われた。
それがどうしてなのか、自分でもよくわからなかった。いや、俺はきちんと理解していた。
なんだよ、それ。俺を飽きもしないで追っかけ回してたのは、岩ちゃんに言われたせいなのか。──そう考えることで、どうして俺がムカついてるのか。それを、理解したくなかっただけ。
「それなら、岩ちゃんに聞けばいいでショ。俺は忙しいの」
「岩泉さんより、及川さんの方がうまいです」
もう一度歩き出そうとしたのに、こいつは本当に、なにを言い出すんだ。俺はもう一度足を止めて、はぁ、と、深いため息をついた。
お前ね、自分がなに言ってるのかわかってるの? 確かにうまいさ、自分のサーブに自信がないわけじゃない。
だけど、こいつはわかっていない。俺が、お前にそれを言われることで、どんな気分になるのかを。嬉しくて、だけどやっぱりムカついて、けれど決して、悪い気はしないのだということに。
「……サーブだけ?」
「え?」
じろ、と見下ろす俺を見て、飛雄は間抜けな顔をした。今まで、『イヤだ』以外を返事をしてこなかったから、そうじゃない言葉を聞いて驚いたようだった。
「教えてほしいのは、サーブだけ?」
「だけ、じゃ…ないです」
ぎこちなく、少し息を上げながら、飛雄は言った。キラキラした目で俺を見て、期待しているのがまるわかりだ。
サーブも、トスも、レシーブも、及川さんは他の誰よりうまい。練習試合であたった他の学校のセッターだって、及川さんみたいにうまくなかった──。飛雄は、早口でまくしたてた。そうして、俺の心に小さく、確かに波を立てる。
当たり前だろ。俺は人一倍練習して、決して妥協なんかしていない。仲間のことを誰よりも、なんていったら岩ちゃんは『俺の方が』と言ってくるかもしれないけれど、そんな岩ちゃんまで含めて、俺はちゃんと考えながらいつもあの場所に立っている。
「及川さんは、他の人よりうまいから。教えてもらうなら、及川さんがいいです」
飛雄、お前はそう言うけどね、きっとお前は、一度教えたらすぐにコツを掴んでしまう。そうして、俺が必死に培ってきた『経験』という武器ですら、『才能』で噛み潰してしまうだろう。
それが俺には、どうしようもなく腹立たしいのだ。腹立たしくて、妬ましくて、だけどちょっぴり、嬉しかったりもする。
「だから、全部です」
「全部って、大きく出たね」
なんて貪欲で、傲慢な奴だろう。俺から、全部さらっていこうというのか。
全部って、どこからどこまで? 技術も、力も、それから、それから──。
「お願いします、及川さん」
今まで、はぐらかしたり拒絶したり、否定的な反応しか示してこなかったから。だから俺が少しばかりの優しさを見せてやるだけで、飛雄が眼の色を輝かせて胸をときめかせているのがわかる。
なんだか笑えてきて、俺は思わず頬を緩めた。そのまま歩き出す俺を追いかけて、飛雄がトタトタと歩き出すのも面白い。
「どーうしよっかな~」
本当に、バカだよ、お前。ルパン三世か、キャッツアイでも気取っているつもりだろうか。
いや、本人にそんな自覚はないのだろうけど。マンガやアニメの中でなら泥棒も華麗だろうが、奪われた後に残るのは、絶望、無力感、失望感──。
「なにしてくれるの?」
「え?」
振り返った俺に驚いて、飛雄は目を丸くした。
「え? じゃないでショ。人にお願いするなら、それに見合った報酬がないと」
そんな簡単に、奪わせないよ。俺はそんなに甘くない。
親指と人差し指で丸を作って、飛雄の前で見せてみる。飛雄は困ってしまったようで、眉を難しい形にして、口唇を尖らせた。
「なにが欲しいんですか?」
「それ、本人に聞いちゃダメじゃない?」
いい顔してるね。悔しそうで、不満そうで。そうやって、俺がいつもどんな思いをしてるのか、お前も少しは思い知ればいい。
「考えといて。それじゃあね」
「なんでもします」
もう、大分家の方まで近づいてきていた。俺の家は住宅街の奥にあるから、今、この道を通る人は誰もいなくて。
ジャージのまま、両手をギュッとグーにして、眉毛をきつく結んだまま、なんてブサイクな顔してるんだ。
「お金は、ないですけど…。」
口唇をとんがらせたまま、飛雄は、ふい、とそっぽを向いた。呆れてしまって、ものも言えない。すぐそこに家があるのに、俺は立ち尽くしたまま、ため息すらもつけないでいた。
バカ。バカ。バカかお前。
中学生の財布なんてたかが知れてる。千円札が何枚かあればいいほうだ。
そうじゃない。『金』以上に、お前になにができるっていうんだ。お前はただの中学生で、バレーが少しうまいだけのただのガキで。相手が可愛い女の子ならまだしも、こんな奴に俺を喜ばせることなんてできるとは思えない。
「…なんでも?」
「俺に、できることなら」
一生懸命考えながら、飛雄は言った。なにをさせられると思っているのか、できるだけ被害を縮めようとしているようだ。
だけど、お前はホントにバカで。だからそれで、どうなるのかがわかってない。それなら、思い知らせてやろう。
俺はきっと、これまでの何ヶ月かのこの関係に飽き飽きしていて、できれば、なにか変化をつけてしまいたかった。それがどんな影響を及ぼすのか──。怖さを、興味深さが凌駕していた。
「じゃあ、俺の家来になってよ」
「家来?」
「そう、家来」
いきなりなにを言い出すのか、と、飛雄のまんまるの眼が言っていた。自分で、『なんでもする』って言ったんじゃないか。俺は笑いを堪えられずに、ニヤニヤと口許を緩ませたまま、飛雄を見下ろしていた。
「荷物持ちとか、荷物運びとか…、ああ、それじゃ荷物係か。なんかあったら、色々言うから」
「そんなんでいいんですか?」
意外な反応だった。てっきり、諦めるとおもっていたから。
「『そんなん』って、ヤじゃないの?」
先輩にここまでバカにされて、二つ返事でOKするなんて、一体なにがお前をそうさせるんだ? 答えはすぐに、飛雄自身が教えてくれた。
「でも、バレー教えてくれるんですよね?」
ああ、なんだ。つまらない。
飛雄は本当に、バレーが好きで。好きで好きでしかたがなくて。今でも十分センスがあるのに、技術も、周りに比べれば全然あるのに、自分が弱いと知っていて、うまくなりたくて、努力を決して怠らない。そんなところが、俺にはすごく鬱陶しくて、ウザくて、妬ましくて、たまらないのだ。
「お前が、ちゃんとできたらね」
「あザス!」
両手の拳をぐっと胸元で握り締めて、飛雄は大きな声を上げた。やめてよ、ご近所迷惑になっちゃうじゃない。だけど飛雄は、そんなことなど気にしないで続けていった。
「なにしたらいいですか? なんでも言って下さい」
「え、今?」
自分で言ったことなのに、俺は、飛雄に命ずるべき『命令』を考えていなかった。どうして、なにをしてもらおう。この、俺の目の前で目を輝かせて、王様から発せられる命令を待ち受けている家来に対して。
「とりあえず今日のところは、『そろそろ帰れ』。俺んちすぐソコだし、そろそろご飯食べたいしね」
「あ…、すみません、遅くまでその、おひ、き…あれ…?」
飛雄がもたつくのを見下ろしながら、俺はどこかで少し、安心していた。こいつは、まだまだガキだ。言葉もマトモに喋れないし、不器用で、下手くそだ。
こんな奴を、どうして俺は今まで怖がっていたのだろう。岩ちゃんの言った言葉が頭を過る。
「お引き止め?」
「それです」
バレーはコートに六人だ。六人で強いほうが強いんだ。
お前の強さは、俺もみんなも、監督もよく知っている。お前がこれからコートに立つ機会は絶対増えてくる。
それなら俺は、お前をどれだけモノにできるかやってみるよ。
「失礼しアす!」
飛雄はそう言って、踵を返して走りだした。ああもう、嬉しそうにしちゃって。これからお前が、どうなるのか知りもしないで。
「影山」
声に出して名前を呼ぶと、すぐに立ち止まって、振り返る。素直で、従順で、いいことだ。だけどね、飛雄。お前に、俺は利用させないよ。
「明日六時、迎えに来てよ」
お前を利用するのは、俺だから。お前の強さまで食い物にして、俺は北川第一を、全国に連れて行く。
「初仕事、ヨロシクね」
にっこりと俺が笑うと、遠くで飛雄が、ぺこりと俺に頭を下げた。俺は飛雄が再び走りだしたのを見届けて、振り返って、歩き始めた。
家の玄関が見えてくる。明かりはついていて、どこからかカレーの匂いまでし始める。
「ヤだなぁ、ホント」
母さんは、ちゃんと俺の気持ちもわかってくれていたらしい。腹が美味さの予感に騒ぎ出し、胸は、楽しさの予感にざわめいていた。
「なんか、楽しくなってきちゃったよ」
明日、本当に飛雄は来るだろうか。いや、きっと来るに違いない。
どんな『命令』でも、きっとあいつはがむしゃらになって応えてくる。さて、どんな難題を押し付けようか──。それを考えながら門を開く俺の口は、きっと笑っていただろう。