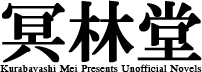本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
家来と王様
[3] 気まぐれ、道連れ、もう手遅れ
「はい、おしまい」
影山の頭を支えにすると、俺はそう言って立ち上がった。くしゃくしゃになった髪を少し気にしながら、絆創膏の貼られた顔を影山は確認していた。
「ありがとうございます」
鼻の頭に出来た傷を軽く触って、影山が頭を下げる。これくらいなにもしなくて大丈夫だとこいつは言っていたけれど、影山の赤い鼻を俺が見ていられなかった。
「風呂入る時、濡らさないように気をつけなよ」
「ウス」
俺の言うことに短く答えて、影山は立ち上がった。バッグを持って、俺が壁際へ歩いて行くのに影山もついてくる。
電気のスイッチの脇に立つと、影山が扉を開けた。もう、部室には誰も残っていない。他の部活の連中もみんな帰ったのだろう。外に出ると少し寒くて、俺は電気を消した後部室の扉に鍵をかけた。
「すみません、すっかり遅くなっちゃって」
階段を降りて、部室棟の外に出る。流石に辺りは真っ暗で、帰り道を照らす電灯を目印に歩き出す。
「別にいいよ。痕になって、及川さんのせいでキズモノになっちゃいましたとか言われても嫌だからね」
影山は不満そうに眉を寄せて、隣を歩く俺をじっと見上げていた。そんなことしませんよ、と、言い出しそうな口をしている。
さっきまでは真っ赤だった影山の顔も、だいぶ時間が経ったからか腫れが引いたように見える。それに少し安心して、俺は鞄を肩にかけると頭の後ろで指を組んだ。
「まったく、ちゃんとボール見なよ」
「及川さんがボカボカ撃ちまくるからじゃないですか」
口唇を尖らせるながら言い返してきた後輩を、俺は思わず凝視した。
どんなところに打っても必死に食らいついてくるものだから、それがなんだか面白くなって、調子に乗ったことは事実だけれど。
「お前ね、それ、カゲレン付き合ってくれてる先輩に言う台詞?」
じっとりと睨みつけると、影山は、う、と声を詰まらせた。もごもごと口を動かして、やがてポツリと呟いた。
「すみませんした」
「わかればよろしい」
ここ最近、影山と一緒にいる時間が前より長くなった。だから俺は、こいつの扱い方について随分学習していたと思う。
偶然にも、影山の家は俺の家からそう離れていなかった。この分なら、こいつを送り届けたとしても飯の時間に間に合いそうだ。
「はーもう、帰ろ帰ろ。すっかり遅くなっちゃったよ」
「あ、鞄持ちます」
「いいよ今日は」
影山は、俺の家来だ。俺はいつも、『これも練習の内だよ』と言って家来に鞄を持たせている。
けど今日は、そういう気にはならなかった。不慮の事故とはいえ、怪我をさせてしまったことへのせめてもの侘びの気持ちだ。
「影山さぁ、今更だけど、まいんちこんな遅くなって親御さんに怒られない?」
腹は大分減っていたけど、今日は買い食いはやめておこう。そんなことを考えながら、俺は他意のないことを尋ねた。
「先輩と練習してるって言ってあるし、うち親遅いんで」
「ふうん。まあ、本当のことだからいいけどさ」
俺たちは部活帰りのジャージ姿で、二人で夜の道を歩いている。誰が見ても、こいつが俺の家来だなんてきっと思わないだろう。
だけどそう言えば、俺はこいつのなにも知らない。どうしてバレーを始めたのかも、こいつの親がどんな仕事をしているのかも。
「どうして、国見だけ『ちゃん付け』なんですか?」
突拍子もない問いかけに、俺の目が丸くなった。腕を下ろすと、鼻に絆創膏をつけた仏頂面に俺は尋ねた。
「なんの話?」
「及川さん、最近国見のこと『ちゃん』付けて呼びますよね」
そうだったっけ、と考えてみる。きっと、きっかけなんてない。なんの気もなく呼び始めて、相手がそれを拒まないから定着しただけの話だ。
「だって、可愛いじゃない、国見ちゃん」
「嫌がってますよ」
「振りだけだよ」
今年の一年は、個性が強い。俺がセッターだったからそう感じるだけなのだろうか。
国見は多分、女のように呼ばれてもそれに心底辟易してはいないはずだ。あいつはそう呼ばれるのを鬱陶しいとは思っても、メリットをうまく活用して振る舞うことができる奴だ。
「金田一は苗字長いからさ」
こいつと二人だけの空気に、俺は大分慣れてきていた。まだ時々、予想外の展開に面食らうことはあるけれど、二年先に生まれた分俺の方が優位でいられる。
「三文字がちょうどいいんだよね、『ちゃん付け』するのに」
俺がおかしなことを言っても、影山は馬鹿にはしない。同い年のチームメイトや幼馴染とこいつは違う。
「そういうもんスか?」
「そういうもんです」
俺がそう言っても、こいつはころっと騙される。俺が岩ちゃんをどう呼んでるのか、こいつは覚えてないのだろうか。
別に呼び方に、意味なんてない。理由も多分後付けだし、呼び方で区別しているつもりもない。なのにどうしてこいつはいきなりあんなことを聞いてきたのか。
「安心しな、お前は呼ばないから」
「呼んで欲しいと思ってないです」
影山は前を向いたまま、俺の言うことに即座に応えた。随分慣れてきたとはいえ、こいつの会話のペースは俺の神経を逆撫でる。
「お前、ほんっと可愛くないね」
「国見は可愛いんですか?」
あ、と、ようやく俺は気がついた。なんだこいつ、回りくどい聞き方をしやがって。
俺は三年で、チームの中じゃあセッターをやっている。だから一年だけじゃなく、部員全員の性格くらいは把握している。
それは俺にとってはごく当たり前のことで、だけど、こいつにとってはそうじゃないのだ。だから他のメンバーとうまくいかずに、無意味な衝突を起こしたりする。
「素直だからね、国見ちゃんは」
お前とは違って、と、俺は口に出さなかった。言わなきゃ気づかないだろうな、と、思っていると意外な答えが返ってきた。
「素直だと可愛いんですか?」
信号待ちで立ち止まった俺の隣に、影山が追いついてきた。まだ成長期の始まったばかりの影山と、既に成長中の俺とでは頭一つ分身長差がある。
「そりゃあ、先輩の言うことちゃぁんと聞ける素直な後輩は可愛いよ」
ニヤニヤしながらそう言うと、影山は眉を寄せてすっかり黙りこくってしまった。俺たちのすぐ近くで、黄色に変わった信号がやがて赤色を点灯した。
「お前、ほんっとそういうのヘタクソだよね」
顰め面の後輩を見下ろしながら、俺は苦笑し、横断歩道を渡り始める。無言で続く影山が邪魔くさそうに鼻をポリポリ掻いていた。
影山を悪く言う二年がいるのは知っている。仕方がない、俺から見ても、彼らから見ても影山の才能は眩しすぎる。
俺の目の届く範囲なら、問題はないはずだ。こいつが周りとぶつからないよう、俺が率先してこいつをイジメているのだから。
だけど、俺の知らないところまで面倒は見られない。今日、二年たちにせっつかれながらモップを掛けていた影山の顔を思い出して、俺は無意識に嘆息していた。
「そんなんだから目ェつけられんだよ」
ひとりごとのように、俺は呟いた。けれどそれをきっと影山は聞いていて、ポケットに手を入れながら難しそうな顔をしていた。
「言うこと聞いて、なんかいいことあるんですか?」
夜の住宅街に人気は少ない。ビニール袋を提げているサラリーマンが駅の方から歩いてきていて、俺たちとすれ違うまでの間、俺は言葉を失っていた。
「あのね。同じ部活の仲間なんだから、少なくとも喧嘩腰はやめなさいって」
まったくこいつは、一体どういう教育を受けてきたんだ。いや、小学生に上下関係なんてあってないようなものだ。中一の今ちゃんと教えてやらないと、迷惑するのはこっちの方だ。
「俺だって素直ですよ」
鞄の紐を直しながら、影山が呟いた。こいつ、どの口でそんなことを言いやがるんだ。呆気に取られた俺の耳に、どこかで犬が鳴くのが聞こえた。
「ちゃんと言うこと聞いてるじゃないですか」
ぼそぼそと、影山は続けて言った。俺を見上げる影山は鼻に絆創膏を貼った間抜け面で、きっと不慣れな台詞を吐いて一生懸命見つめてくるものだから、なんだか可哀想だと思った俺は大分絆されている。
「俺以外にも素直になんなさい」
「命令ですか?」
「命令です」
影山は、俺の家来だ。だから俺の命令は聞く。ああ、こいつは素直な奴だ。
素直で単純で正直で、嘘なんてきっとつけない。こんなに憐れでバカで不器用でヘタクソな奴なのに、なんだかカッコいい奴のような、気がしたようにも思わなくもない。
「わかりました」
影山はそう言うと、前を向いて頷いた。失敗したか、と、俺は思った。こいつの場合、きっと素直になることよりも歯に衣着せることを学んだ方がいい。
だけど、そんなこと出来るのだろうか。短い付き合いではあるけれど、影山ときたらやることなすことバレーのことばっかりで、頭が良い方であるとは思えない。
「……影山って、下の名前なんだっけ」
少し喉が乾いてきて、俺はバッグのポケットに入れていたペットボトルを取り出した。電解質の入ったスポドリは喉にするりと流れこみ、俺の乾きを癒しながら腹の中に落ちていく。
「飛雄ですけど」
「ふうん」
とびお、と、俺は心の中で彼の名前を呟いてみた。なるほど、よく似合う格好の良い名前じゃないか。
こいつはそうやって、バレーのネットも俺たちも軽々飛び越えていくんだろう。こいつがどこまで高く飛べるのか、その背中を、その姿を、見てみたい、と、俺は思った。
「トビオちゃん」
スポドリで濡れた口唇は、甘くて酸っぱい味がした。ぺろりとそこを舐めとって口に出すと、その言葉は思ったよりも余程自然に俺の声に馴染んでいた。
「は………?」
自分が呼ばれたことに、飛雄は気づいていなかった。大きな目をぱちくりと瞬かせて、俺のことを凝視している。
こうして見下ろすと、俺の想像の中にいた飛雄との違いに思わず笑えてくる。街灯に照らされた肌は白く、子供らしくふっくらしていて頬を掴んで引っ張ったらきっと柔らかいんだろう。目を皿のように丸くしていて、鼻には絆創膏を貼り付けている。なんだ、恐がるまでもない。飛雄の顔を面白いと思うのは、きっとこれが初めてだった。
「やめてください」
「なんで? そう呼んで欲しかったんじゃないの?」
飛雄は頬を膨らませて、早足でズカズカ歩く。少しだけ中身の残ったペットボトルを右手で摘んで、飛雄を追いかける俺の顔には自然と笑みが浮かんでいた。
「そんなこと言ってないです」
「あれ~? 絶対そうだと思ったのに」
飛雄相手に、嫌味は効かない。こいつの場合は真っ向から揶揄った方が愉快な反応を返してくる。
それに気がついた俺は、ようやく飛雄を面白がれるようになった。握っていたペットボトルの口を開けて、笑い出しそうな口を窄めてゴクゴクと喉を潤した。
「いいね、『トビオちゃん』て。三文字だし、バカっぽくて」
チラ、と様子を窺うと、飛雄は案の定眉を寄せて、ジロリと俺を睨んでくる。だけど、ダメだよ。頬が困惑で引き攣っている。嫌がってはいたとしても、嫌ってはいない証拠だ。
「バカっぽいってなんですか」
「ホントのことじゃん」
空になったペットボトルを掴みながら、俺たちは小さな公園に足を踏み入れた。ここを突っ切ると家に向かう近道になる。そして、この先の右と左で二人の帰り道が分岐するのだ。
公園には、ブランコと滑り台、ブルーシートの貼られた砂場。小さなベンチ、公衆トイレ、それから出口の近くには自動販売機が寂しげに立っている。
ゴミ箱も置いてあるから、手の中にある空のボトルをそこに投げるのがいつもの日課だ。けれど今日は、そうする気にはならなかった。もっと面白そうなことを思いついてしまったから。
「トビオちゃん、いっくよ~!」
「ゎ、ちょ、え!?」
公園の真ん中で、俺は大きな声を出した。バレーのサーブとは違うフォームで、空のボトルを放り投げる。
アホっぽい声を出して、飛雄が慌てて駆け出した。鞄を地面に放り投げて、ご自慢の俊足でゴミを追いかけていく。
中身が空だったからなのか、あまり遠くの方には飛ばなかった。フェンスにぶつかり、コロコロ転がり、それを拾った飛雄がすかさず俺の方へと走ってきた。
「いきなり、なにさせるんですか」
少し息を弾ませながら、飛雄は言った。今度はもっと広い場所で、ボールでも持ってこようと、俺は思った。
「偉いね~、ちゃんと取ってくるの」
俺だけの家来に対する労いの気持ちがあって、我ながら珍しく率直に褒めてやった。俺が手を出し待っていると、飛雄は眉を寄せて口を尖らせ、それでも静かに空のペットボトルを俺へと差し出してくる。
「嫌じゃないの? 先輩にいいように使われて」
「及川さんなら、嫌じゃないです」
本当に、こいつの会話のテンポには俺はいつも驚かされる。テンポだけじゃない。まっすぐ俺を見つめながら飛雄の放つ言葉の意味に、俺は目が醒めるほどの動揺と、呼吸が苦しくなるほどの混乱を味わうんだ。
「バレー、教えてくれるんですよね」
瞬きをした飛雄の瞳が俺を射抜いて、俺は、ずがん、と頭の裏に響くような衝撃を味わった。それは岩ちゃんに殴られた時にも似ていて、だけど、決して痛くはない。ただ、どうしようもないほど苦しくて、それがなぜだかすぐにわかって、俺は自分の愚かさに瞬時に痛感させられた。
「及川さん?」
答えないでいる俺を見上げて、飛雄が追い打ちをかけてくる。やめろ、来るなと思っていても、飛雄には伝わらない。
俺は、なんてバカなんだ。どうして今まで平気でいられたのだろう。
気づかないでいた間抜けさと気づいた自分の優秀さの両方に責め立てられて、無意識の内に力が入って、ペットボトルを凹ませそうだ。自分自身で制御出来ない困惑が伝わる前に、飛雄を前に立たせたまま、俺は小さく呟いた。
「トビオちゃん、目、閉じて」
低い声でそう言うと、飛雄は不審に思いながらもいつもの従順性を発揮した。今くらいは、反発してくれてもよかったのに。いや、飛雄がそうしてくれなければ、参ってしまうところだった。
ふう、と、俺は細い息を吐いた。目の前にいるジャージ姿の無防備な後輩を、俺は持て余していた。
「上向いて、動かないで」
吹き出しにクエスチョンマークが浮かんでいそうな顔をしながら、飛雄は俺の言う通り、拳を握って顎を上げた。飛雄の鼻の頭の上には俺のやった絆創膏が貼られている。なんて間抜けな顔なんだ、と、思う一方で俺は何故か緊張してごくりと息を呑んでいた。
俺がバレーをしていなければ、こいつはこうして俺と一緒に帰ることも、投げたゴミを拾うこともなかったのだろう。こいつが俺と同じ学校に通ってなければ、飛雄がこうして俺の前で呑気な恰好をすることもなかったはずだ。
俺はきっと、期待していた。飛雄が俺についてまわる理由の中に、『及川徹』という特別が少しでもあればいい、と。だけど、こいつは最初からバレーのことしか考えてない。バレーがうまい先輩であれば、きっと俺が及川徹でなくても構わなかったんだろう。
そう思うと悔しくて、俺は口唇を噛み締めた。どうして悔しいと思うのか、俺は多分わかっていた。
俺はこいつに、知らしめたい。俺が俺であるのだ、と。ちゃんと俺を追いかけろ、と。
俺を見て、俺を感じて、俺に夢中になればいいのに。俺がそう思っているのを知らずに、飛雄は不安げな声を洩らした。
「及川さん?」
「喋んな」
そんな風に、俺を呼ぶな。冷静でいられなくなる。
今飛雄は、きっと俺に頼るしかない。不安も焦りも俺のせいで、だけどこいつを救えるのも残念ながら俺だけなのだ。
言葉を奪われ声を塞がれ、飛雄は、きゅ、と口を噤んだ。頼りなげに震えている飛雄の口唇を見つめたまま、俺はもう一度息を呑んだ。
俺は、どうしたらいいんだ。やめろ、だめだ。それをしたらきっと誤魔化せなくなる。
誰に、飛雄に、他には、自分に。それから、それから、それから、それから──。
ギリッ、と、俺は口唇を噛み締めた。そうして俺は握っていたボトルを飛雄に押しつけた。
え、と、小さな声を上げた後、飛雄が胸のあたりを押さえて俺からボトルを受け取った。俺は飛雄を押すようにして距離を取ると、飛雄に表情を見られないように踵を返し、歩き出した。
「それ、捨てておいてね」
飛雄はきっと、目を丸くして俺を見つめているんだろう。俺がなにを考えていたか、あいつにはわからない。
それでいい、それでいいんだ。早く終わりにしてしまおう、と、背中を向けたまま手を上げる。
「じゃあね」
「あ、及川さん」
帰ろうとする俺に向かって、飛雄が声をかけてきた。なんだよ、邪魔しやがって。聞こえない振りをしても良かったのだろうけれど、そうするとなんだかホントに逃げているみたいだったから、出口の脇で足を止めて、俺は飛雄へ振り返った。
「明日も、いつもの時間に行きますから」
そう言う飛雄は大事そうに、両手で空のペットボトルを握っていた。さっきまで、自分がどれだけ危険な立場にいたのかも知らないで。
「わかったから、早く帰れ」
はぁ、とため息をつきながら、俺はひらひらと手を振った。それを見た飛雄はぱっと顔を明るくして、両手を脇にぴたりとつけて深々と頭を下げた。
「お疲れっした!」
もうすっかり夜なのに、飛雄の声は住宅街によく響く。仲間だと思われないように、俺はそのまま歩き出して決して振り返らなかった。
鞄を担いで、飛雄が夜道を走っていく音が聞こえた。飛雄と自分の距離が遠くなっていくのを感じながら、俺はようやく安心して、ゆっくりと息をついた。
影山飛雄は、可愛くない。厄介な後輩だ。
なのに俺は、影山飛雄がこんなにも気になっている。飛雄の中に自分の存在を植えつけたいと願うほど、いつのまにか俺は飛雄に執着してしまっている。
「ああ、もう」
苛立ちを声に出して吐き出すと、少しだけ楽になった。けれどすぐに苦しくなって、俺は足をいじめるみたいにアスファルトを踏みつけた。
早く帰って寝てしまおう、そうすればきっと少しはマシになれる。ああ、ダメだ。朝飛雄が迎えに来る。なんだ、逃げ場なしかよ、と、家来になれなんて言い出した過去の自分が恨めしくなる。
いやだ。なんとかなるはずだ。大丈夫だと思いたい。俺は多分器用だから、きっとうまく出来るはずだ。きっと腹が減っているから弱腰になってるだけだ。
不安は胸の中に渦巻いていて、体中に広がっていく。それをやっつけるために、今日はたらふくメシを食おう。
早足に家に帰り着くと、噛みつくようにドアを開けて俺は家の中へと急いだ。乱暴に靴を脱ぎ捨てて、部活のジャージ姿のままリビングへと滑りこむ。
大丈夫、大丈夫、と、俺は繰り返し言い聞かせた。本当に? と、尋ねてくる誰かの声に耳を塞いで、俺は青色の箸を掴むと、『いただきます』の呪文を唱えた。