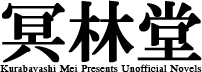本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
柔らかな檻
[4] お前なんか仲間じゃない
いつのまにか、そこはとても静かになった。他の人間の気配が消えて、晶馬だけが世界から切り取られ、置き去りにされていた。
晶馬を散々蹂躙した快楽は、未だ彼の躯の中で燻ぶっている。初めての快感は幼い少年を淫らに変えて、現実と夢との境を奪ってしまった。
晶馬は、床にうつ伏せに横たわっていた。無様に這いつくばったまま、晶馬は、おかしな幻想の中にいた。
体は重く、身動きができない。それなのに、なぜか宙を浮かんでいるような、異常な感覚を味わっている。
吐き出す息が顔にかかって、生温かい。冷たい床は晶馬の温もりと溶け合って、まるで、自分が部屋の一部になってしまったかのようだ。
晶馬はひどく疲弊していて、体力を激しく消耗していた。頭は真っ白で、心は空っぽで、晶馬は自分が目覚めたことにすら、気づくことができなかった。
その日、晶馬を襲った出来事は、到底受け入れられないことだった。晶馬は未だに、なにが起きたのか把握できていなかったし、理解することもできなかった。
強烈すぎた悦楽の余韻に、もうどれだけたゆたっていただろう。ぼうっとしていた頭は、とりとめもない思考を紡ぎ始めた。
──ここは、どこ?
自分がどこにいるのかを、晶馬は忘れてしまっていた。起き上がって、あたりを確かめる気にもなれない。晶馬は、焦点の合わない瞳に映る景色を、ただ無感動に眺めていた。
カーテンの向こう側から、温かい色の夕日が射しこんでいる。斜めに注ぐその光は、晶馬の上に、線上の影を落としていた。
ベランダの、何本ものパイプをつないだ簡素な手すり。晶馬の体を跨ぐようにして落ちる影は、まるで格子のようだった。
──どうして僕は、こんなところにいるんだ?
それは、晶馬の頭の中だけの呟きなのか、実際に口に出しているのか、自分でもわからなかった。ぱちりと瞬きをすると、凍結していた思考がゆるゆると働き始めた。
──ああ、そうだ。ここには、父さんと母さんが連れて来てくれたんだ。
家を出たのは今朝のはずなのに、まるで遠い昔のことのように感じられた。晶馬は、ばらばらな記憶を集めるように、これまでのことを順繰りに思い出そうとした。
大人になるために、立派な人間になるために、必要なことなのだと言っていた。これはとても大切なことで、それを教えてもらえる晶馬は特別で、選ばれた子供なのだと言っていた。
みんなのいうことをよく聞いて、しっかり勉強するんだ。大丈夫、ちゃんと迎えにきてあげるから。
本当に? いつまで? ──考えるのも面倒だった。
反抗や反発には、気力と体力が必要だ。けれど、そのどちらも、既に折られてしまった。あとはただ、絶望に打ちのめされてしまわぬように、全てを遮断するだけ。
日は翳り、夜が落ちてくる。異様で、不気味な状況だった。耳鳴りがするほどの静寂。なにも動いていない、変わっていないのに、時間だけが過ぎていく。
きっとこの部屋は、他の世界とは違うのだ。同じ建物に他の住人が住んでいるなど、到底考えられない。
大きな建物には、いくつもの小さな部屋が存在している。けれど、その中で起きる出来事に、誰も気づかず、無関心だ。
きっと今、晶馬がこうして横たわっていることも、誰も知らない。他の人間がなにをしているのか、晶馬が知らないのと同様に。
晶馬は、生まれて初めての孤独を感じていた。寒い、と感じた。体は汚れたままだったし、太陽の温もりも夜に食われてしまったから。
ぶる、と、身震いをした晶馬の耳に、小さな音が届いた。それはとても微かなものだったから、聞き間違いではないか、と、晶馬は自分を疑った。
どんよりとした甘い臭いで、鼻はすっかり馬鹿になってしまった。それでも、晶馬は僅かに顔を上げて、鼻をひくりと動かした。
これまで全く気づかなかった、人の気配がする気がした。同じ壁の内側で、自分と同じように、息を潜めている者がいる。
晶馬の視線が、床の上を転がった。自分のすぐ近くから、段々と裾を広げてみる。
床に散らばる液体はすっかり乾いてしまって、脱ぎ散らかされた晶馬の服がところどころに転がっている。その向こう側、ずっと奥の部屋の隅に、晶馬とお揃いの靴下を履いた爪先が見えた。
晶馬の胸が、ギクリと高鳴った。どうして今まで気づかなかったのか。いつからそこにいたのだろう。気づかないのも無理はないと思えるほど、ひっそりと、けれど確実に、一人の少年がそこにいた。
闇の中で、彼は壁に背を向けて、晶馬をじっと見つめていた。声も出さず、瞬きもせず、大きな瞳で晶馬を見つめている。
「きみは誰?」
晶馬は、震える口唇を動かした。きっと、小さな声だった。もしかしたら、声にすらならなかったかもしれない。
「お前こそ誰だ?」
冷たい声が、冷たい部屋にはよく響いた。これまでずっと沈黙を保っていた彼の声は、静かであったのが嘘のように、晶馬の心を揺さぶった。
晶馬と、冠葉。
二人の人生が、交わった瞬間であった。
冠葉は、晶馬よりも少し前に、この部屋に連れられてきた。冠葉は、彼の父親に『才能』を見込まれていた。だから、同じに日に産まれた真砂子ではなく、冠葉だけが、この部屋に入ることを許されたのだ。
冠葉は、この部屋の意義と、自分が連れられてきた意味を知っていた。父親が自分になにをさせたいのか、自分がどうすればいいのか、わかっていた。
だから冠葉は、その通りに振舞った。大人たちは、皆喜んだ。皆は、優秀であった冠葉を持て囃し、褒め称え、熱心に『教育』した。
冠葉にはわかっていた。自分はきっと、何者にもなれない。将来への夢や希望なんて、なにも知らない子供だけが罹る、病気みたいなものだ。
父が用意した狭い世界で、父の望む自分でいること。それだけが、冠葉と父が家族でいるための、冠葉が真砂子の望む世界を守るための、唯一の方法だった。
そんな冠葉にとって、泣き喚き、慌てふためき、抵抗しようともがく晶馬は、愚かで、憐れな姿に見えた。だから教えてやったのに、今も尚、事態を理解できずに狼狽している晶馬を見つめ、冠葉は小さなため息を漏らした。
「そんなはずない、嘘つくな!」
大きな瞳を揺らして、晶馬は震える声で怒鳴った。けれど、冠葉は冷静だった。動揺している晶馬に対し、冠葉は無感動で、無関心だった。
「嘘だと思いたいなら、構わないぜ。好きにしろよ」
でも、俺は嘘はついてない。冠葉は続けて言い放った。その言葉は、晶馬に残酷な事実をつきつけた。
ここは、気持ちのいいことだけに満ちた、気持ちよくなるためだけにある世界。この世のどこよりも気持ちのいい世界の住人に、晶馬は選ばれた。
それが子供にとって、どれだけ屈辱的で、どれだけ恐ろしいことで、どれだけ悲惨なことであるかなど、誰も気づいていない。むしろ晶馬は、彼らにとっては、世界中のどの子供よりも幸福な存在だった。
「………いやだ」
今度ははっきりと、晶馬は呟いた。
体が震えているのは、もはや寒いからではなくなった。起き上がろうと体を動かすと、身を劈く痛みが、なんとかして逃げださなければ、と、晶馬の気を逸らせた。
「出口はあっちだ」
冠葉の指が、玄関の方を指し示した。それは昼間、晶馬が潜った何の変哲もない扉だった。
「鍵は内側から開く。行くなら行けよ」
冠葉は、面倒くさそうに、ぶっきらぼうな口調で言った。腕を丸め、再び膝を抱える冠葉を見て、晶馬はゆっくりと瞬きをした。
なんだか、あっけないような気がした。閉ざされた扉は、いとも容易に開くという。
「服は着ていけよ。そのカッコじゃ、風邪ひくぞ」
晶馬は、はっとして、自分を見下ろした。晶馬の体の至るところには、子供らしからぬ赤い腫れができていた。
晶馬は、裸のままだった。粘液で汚れた自分の体を恥ずかしがって、晶馬は慌てて、周りに落ちていた自分の服を拾い上げた。
「きみは、行かないの?」
服で体を隠しながら、晶馬は尋ねた。冠葉は相変わらず座ったままで、ぴくりとも動かなかった。
「待ってるんだ」
なにを、と、晶馬は思った。出口を知っているくせに、どうして彼は行こうとしないのだろう。
ぐずぐずしていたら、また奴らが来るかもしれない。こんなところで、なにを待っているというのだ。
シャツの袖に腕を通し、頭を潜らせ顔を上げると、晶馬は、虚ろに見えた冠葉の瞳に射竦まされた。
「──父さんを」
自分ではない誰かに出会えたこと、それが、自分と同じくらいの年の少年であったことで、晶馬は少し、励まされていた。無気力であった晶馬の心に、身を起こし、逃げだそうとする元気が生まれた。
冠葉の小さな呟きは、重い響きでもって、晶馬の体を縛りつけた。
晶馬をこの地獄のような場所に連れて来たのは両親で、晶馬に、あの痛烈な『快楽』を教えこんだのは、晶馬の父親だった。
それはきっと、晶馬のためを思ってしたことなのだ。横暴で、乱暴で、盲目的な家族愛の副作用だ。
迎えに来ると言っていたのに、逃げ出そうとすることは、彼らに対する反逆行為だ。彼らは晶馬を信じ、期待していた。晶馬が熱心に勉強して、立派な人間に、一人前に成長することを。
「でも………」
晶馬の口唇が、震えていた。それが彼らの望みであったとしても、耐えられるはずがない。こんなことが許されるはずがない。そう自分に言い聞かせながら、晶馬は服の裾を握りしめ、噛みしめるように呟いた。
「でも、またあんなことされたら……、死んじゃうよ」
「だから、お前は行けよ」
冠葉の言葉は、辛辣だった。貧弱な自分を許されているはずなのに、なんだかひどく、悪いことをしようとしている気にさせる。
「俺は、父さんを裏切らない」
まっすぐな瞳で、冠葉は晶馬を見つめていた。晶馬の胸は、どきりと跳ねた。冠葉があまりにも、綺麗な眼をしていたからだ。
だから尚更、晶馬は自分が悪いような錯覚に陥った。冠葉の方が正しくて、自分が間違っているのではないだろうか。否定したい疑念が、晶馬の胸を侵蝕した。
ここから逃げると、晶馬は両親を裏切ることになる。眩しくて温かい母さんの笑顔を、もう二度と見ることができなくなるかもしれない。
厳しいけれど優しい父さんの掌で、撫でてくれることもなくなるだろう。彼らは落胆し、晶馬を軽蔑して、家族と認めてもらえなくなるかもしれない。
そう思うと恐ろしくて、だけど、どうしたらよいのかわからなかった。服を着て、準備は整ったはずなのに、晶馬の足は固まってしまった。
体が動かなくなると、思考がやけに早く回転し始める。沈黙の重たさに包まれながら、晶馬は、ポツリと、脳裏に浮かんだ問いを口にした。
「冠葉は、いつからそこにいたの?」
冠葉がこの部屋にいたことに、晶馬は気づかなかった。晶馬の後に連れられて来たのなら、少しくらいは物音がするはずだ。けれど、そんな記憶は一切ない。
「ずっと、そこにいたの?」
冠葉は、この部屋の意味を晶馬に教えてくれた。晶馬の認めたくなかった事実を、彼は既に受け入れている。
それはきっと、冠葉が、晶馬よりもずっと前からこの部屋にいたからなのだ。そう思うと、晶馬の胸はきりきりと痛みだした。
「見てたのか?」
晶馬はこの日、何人もの大人に囲まれて、好き勝手に弄りまわされ、ありとあらゆる辱めを受けた。思い出すのもおぞましい、忘れたい記憶だ。そして、きっとその時も、冠葉はこの部屋にいた。
「助けて、くれなかったのか」
晶馬はそう尋ねたけれど、答えはわかっていた。晶馬の思った通り、冠葉は口を噤み、声を呑み、決して否定しなかった。
どれだけ懇願しても、誰も止めてくれなかった。助けて欲しいと叫んだのに、誰も助けてくれなかった。
絶望的な状況下で冠葉に出会い、晶馬は冠葉が仲間であると錯覚した。いや、仲間であってほしかった。
けれど冠葉は、晶馬の問いかけにも期待にも、応えようとしない。口唇を結び、座りこんだまま、否定も言い訳もしない冠葉を見下ろし、晶馬は、今日何度目かの絶望に打ちのめされていた。