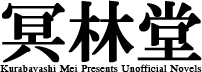本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
フタゴロール
[2] 抜いてやるよ
「サンちゃん、そっちお願いね」
陽毬はしゃがみこんで、ペンギンと一緒になって、布団を転がしていった。下敷きにしていた布団が巻きついてきて、僕は青くなって、うろたえてしまった。
「ちょ、陽毬!?」
「待てって、うわっ!?」
僕らは抵抗しようとしたけれど、女の子相手に乱暴はできない。あんまり暴れると、陽毬が怪我をするかもしれない。それに、転がっていくうちに二人の位置がどんどん入れ替わるから、体同士ががぶつかって思うように動けなかった。
「喧嘩ばっかりするお兄ちゃん達なんて、布団でぐるぐる巻きにしてくれるわ!」
陽毬は楽しそうだった。か弱い女の子の、どこにそんな力があるのだろう。
まるで江戸時代の悪代官のような口振りで、陽毬は3号と一緒になって、僕らに布団を巻きつけていった。仕上げとばかりに持っていた紐でぐるぐると縛り上げて、きゅ、と結び目を硬くする。
暑くて、苦しくて、布団の中から顔を起こすと、すぐそこで同じ苦しさを堪えている兄貴の顔があった。
陽毬は、パンパン、と手を叩いて、畳の上で情けない恰好で転がっている僕らを見下ろした。
「二人とも、ロールキャベツみたいだね」
陽毬は満足げな笑みを見せ、3号も額の汗を拭っている。1号と2号は僕らを助けることもせず、勝手にタオルに巻かれて転がっていた。
「陽毬…、それが言いたかったのか」
眉を寄せて、ため息交じりに兄貴が呟く。
「だって、もう御夕飯食べちゃったでしょ?」
ロールキャベツは、『仲直り』のしるしだ。いつの間にか浸透した我が家のルールではあったけれど、僕らがロールキャベツにさせられるのは初めてだ。
「明日の朝までに、仲直りしておいてね」
陽毬はそう言うと、ふすまに手をかけた。すまきになった僕らへと、陽毬は手を振って挨拶する。
「晶ちゃん、冠ちゃん、おやすみ」
「おい、陽毬!」
「待って、ほどいてよ!」
可愛い可愛い僕らの妹は、電気を消して、兄たちの悲痛な声など無視して、行ってしまった。僕らはしばらく唖然として、閉じたふすまを凝視していた。
「………はぁ」
兄貴は、重いため息を漏らした。兄貴は僕の上に被さっていて、温い空気が頬にあたって気持ちが悪い。
「明日の朝まで、このままか…」
ため息をつきたいのは、こっちのほうだ。僕は依然、ふすまのほうを見つめながら、これから先のことを思って、絶望感に駆られていた。
「勘弁してよ…」
狭いし、暑いし、苦しいし。普段枕を並べて寝ているとはいえ、兄弟一緒に包まれていては眠るに眠れない。
ため息を漏らそうとした僕の上で、兄貴がゴソゴソと動き始めた。
「ちょっと、動くなよ」
兄貴は体を揺さぶって、紐を解こうとしていた。もしくは、引きちぎろうとしていたのだろう。
僕を床に押さえつけて無理に起きようとするから、僕は苦しくなって、顔を歪めた。
「痛いって、兄貴」
「ずっとこのままでいるつもりか?」
僕は言葉に詰まって、口唇を噛んだ。離れられるものなら離れてしまいたかったけれど、兄貴の頑張りも、どうやら徒労に終わったようだ。
「そうだ、あいつらに頼めば…」
僕は顔を横に振って、傍にいるはずのペンギンたちを探した。しかし、彼らはどっちもタオルに絞めあげられていて、青い顔で転がっていた。
「役に立たない奴らだな」
残念そうに、兄貴は舌打った。お手上げだ。僕は今度こそ、深いため息を吐きだした。
僕の吐息を避けるように、兄貴が顔を横向けた。今のままでは、距離が近すぎる。せめてもう少し離れたくて、僕は兄貴の胸を押し上げた。
「兄貴、重い…」
「仕方ないだろ、我慢しろ」
僕の腕は、二人の間に挟まれていた。兄貴の腕は、どうやら僕の腰のあたりにありようだ。
それだから、兄貴は自分で体重を支えることができない。仕方なく、僕は兄貴の重みを全身で引き受けた。
引き受けたつもりだったのに、そんなに重みを感じなかった。兄貴は、僕の脇についた手を突っ張らせ、体重を和らげていたのだ。
そういえば、僕の脚の間にも、兄貴の膝が挟まっている。苦しい姿勢で体を浮かせて、僕に重さを感じさせないように精一杯我慢しているのだ。
ようやくそれに気づいた僕は、なんだか切なくて、申し訳ないような気持になった。
「――制服」
ふすまの向こうのテレビの音は、いつの間にか消えていた。きっと、陽毬も自室で眠っているのだろう。
兄貴の湯上りの髪も、大分乾いてきていた。当初の動揺も薄れ、リンスの香りに包まれて、刺々しかった僕の心も少し和やかになってきた。
「…皺になっちゃうな…」
兄貴のため息も聞こえるような静かな部屋だったから、僕の呟きは大きく響く。兄貴は部屋着に着替えていたけど、僕は制服を着たままだ。
「そうだな」
兄貴は、少し笑ったようだった。含んだ笑みの吐息が首元にかかって、くすぐったかった。
「歯磨きもしてないし」
「朝にしとくか」
「うん」
仲違いがあっても、少し時間が経って気分が落ち着けば、普通の会話もできるのだ。我ながら簡単な人間だとも思うし、先ほどまでのささくれ立った感情はなんだったのかと思いもするけれど、それが兄弟の気安さなのだ。
僕と兄貴は、別の人間だ。外見も性格もそんなに似ていないし、意見が食い違うことも少なくない。
こんなに近くにいるのは、母さんのお腹の中にいた時以来なのかもしれない。そう思うと、暑苦しくて鬱陶しかったこの状況も、少し懐かしいような気になった。
「――ごめん」
俯くと、兄貴の肩に顎が埋まった。兄貴は首を傾げたけれど、その位置からは僕の顔は見えないはずだ。
だから、僕は比較的に抵抗なく、謝罪の言葉を口にした。こんな顔を見られてしまうのは、恥ずかしい。
「でも、荻野目さんから日記を無理やり奪うことはできないよ」
兄貴は黙ったままで、僕は、口早につけたした。それは別に、荻野目さんのためを思うからじゃない。倫理的に、常識的に、正しいとか正しくないとかも関係ない。
僕はただ、臆病なだけなのだ。嫌われること、詰られること――、これ以上を罪を重ねることを、恐ろしがっているだけなのだ。
「もういい」
自分の惰弱さに反吐が出る。ふつふつと湧き起ってくる苛立ちと怒りを堪えようとする僕の耳に、兄貴の囁きは優しく浸みこんできた。
「俺は寝る。お前も、もう休め」
兄貴は、卑怯者の僕の代わりに、いつも矢面に立ってきた。荻野目さんの家に忍び込んだ時も、僕を庇って、汚れ仕事を買って出た。
兄貴はいつもこうやって、僕を甘やかす。『数時間早く生まれた分』にしては、大きすぎる負担をしょってくれている。
荻野目さんを僕に託して、兄貴はきっと、僕にできない役割を演じているのだ。僕が一番イライラしたのは、そんな兄貴のように生きられず、聞こえの良い言葉で体裁を取り繕っている、不甲斐ない僕自身だった。
「うん」
兄と弟の『仲直り』に、多くの言葉は必要ない。そんな兄弟の気安さに、僕は今夜も感謝した。
目を閉じ、兄貴の吐息と体温を感じていると、なんだか心が落ち着いた。もっと、寄りかかってくれて構わない。そんなことでしか、僕は兄貴に応えることができないのだから。
もっと受け入れやすい恰好を探そうと、僕は少しだけ身じろいだ。僕の腹の上で兄貴が浮いて、僕の胸に落ちてきた。
内臓が圧迫されない分、少しだけ楽になった。両手を兄貴の肩に乗せて、肘を上げ、兄貴がバランスをとれるように脇を開けた。
狭い場所を有効に活用するために、居心地よくするために、肢を動かした僕は、ふと、気がついた。僕の右足の上に兄貴の体があって、僕の股間に、兄貴の右足が挟まれていた。
「ぁ……!」
「ん?」
僕は思わず、小さな声を出してしまった。それに気づいて、兄貴が顔を上げた。
「ごめん、なんでもない」
眠ろうとしていたところを邪魔してしまった気がして、僕は慌てて謝罪した。兄貴は不審げな顔をして、また俯いてしまった。
この位置だと、股間が兄貴に重なってしまう。こんな状況で、反応してしまったらどうしよう。
僕は、一人で勝手に動揺していた。もしそうなったら、気づかれないわけがない。
勃っちゃだめだ、そう意識すると余計にドキドキして、僕はなんでもない風を装って、兄貴を遠ざけようと試みた。
「ン……」
口唇を丸めて、両腕で兄貴を押しあげる。僕の上からどかそうとしたけれど、布団を縛るロープが邪魔をした。
「なんだよ」
ムッとした顔で、兄貴は尋ねた。見下ろしてくる兄貴の視線を感じたけれど、僕はバツが悪くて、視線を逸らしてしまった。
「いや、もうちょっと、離れられないかなって…」
「狭いんだから、大人しくしろよ」
兄貴の言うとおり、布団の中は狭かった。ロープで何重にも、ぎゅうぎゅうに縛りあげられていたから、身動きがとれない。
兄貴は再び、僕の上に落ちてきた。と同時、二人の位置は少しずれて、兄貴の腹が僕の股間に重なった。
「あ……!」
「今度はなんだよ」
兄貴は、面倒くさそうな顔をした。僕はどんな顔をしていただろう。きっと情けなくて、醜い顔をしていたに違いない。
「なんでもないんだ」
「ないことないだろ」
「なんでもないんだってば」
僕は少し、大きな声を出した。必死に否定すれば否定するほどわざとらしい気がしたけれど、兄貴は不審げな顔をして、僕を睨みつけるだけだった。
なにも考えず、さっさと眠ってしまおう。仲直りも終えたことだし、朝になれば、きっと陽毬も気が済んで、僕らを解放してくれるに違いない。
だから僕は目を閉じて、声を潜め、息を整えた。寝ようとしている僕を見下ろすと、兄貴は小さく息をして、ゆっくり力を抜き、僕に体を投げ出してきた。
兄貴の体重を、僕の体が受け止めた。二人の距離はいつになく近く、体の半分が兄貴と密着していた。
柔らかい生地を纏った兄貴の肌から、温もりが伝わってくる。暗い中で目を閉じると、意識は自然とその場所に集中してしまった。
ここ最近、全然そういうことをしていなかったから。陽毬が退院して、またあの頃のように、毎日一緒に暮らし始めて。陽毬に、いやらしい姿を見られたら大変だ。
陽毬が入院している間は、兄貴と二人きりだった。子供のころは、両親のいない心細さと、陽毬が病気であることのプレッシャーとが重なって、二人で慰めあうこともあった。
昔はあの『行為』の意味なんて知らなかったし、知るようになっても、もう手遅れだった。僕たちはお互いの手の中で性欲を吐きだして、一つに繋がったこともある。
だけど、僕らが高校にあがってからは自然と回数も減っていったし、陽毬が退院してからは、一度もしていない。かといって、あの快感はそうそう忘れられるようなものじゃない。
優しく包み込んで、柔らかく狂わせて、突き抜けるように連れ去っていく、あの強烈な快楽は――。
「ふ……」
ぞくりと背筋に震えが走って、僕は小さな息を漏らした。体を駆け抜けた悪寒に、体がビクリと竦んでしまう。
別に、寒いわけじゃない。この感覚には覚えがある。思い出してはいけない感覚だ。
「ン……」
僕は腰を引き、体をずらそうとした。布団に腰がめりこんで、畳の感触が伝わってくる。
「だから、なんなんだよ、お前は」
大人しく黙っていたけれど、兄貴はしっかり起きていたようだ。背を浮かせて起き上がって、僕を覗きこんでくる。
「なんでもないって…」
「いい加減にしろよ。下でモゾモゾ動かれると、俺が寝られな……」
違和感に気がついて、兄貴が言葉を濁らせた。僕の胸は、ドキリと跳ねあがった。反射的に目を開けると、驚き凝視する兄貴の視線が、僕を捕まえていた。
悪寒に震えたはずなのに、僕の下半身は、スラックスの中で熱を持っていた。血を集め、形を変えてしまったことに、これだけ近くにいて、兄貴が気づかないわけがない。
「晶馬……」
兄貴を見ていられなくて、見られているのも辛くなって、僕は目を閉じ、顔を逸らした。それでも、体の変化は誤魔化せない。
恥ずかしかったし、呆れられるのは嫌だった。顔が熱くなるのを感じながら、僕は兄貴を掴んで、押しやった。
「仕方ないだろ…」
男の子なんだから、こうなるのは当然だ。そう自分に言い聞かせるけれど、やっぱり恥ずかしいものは恥ずかしい。
簡単に勃起してしまった自分も、それを知られてしまったことも。
「しようのない奴」
兄貴は、呆れた声で呟いた。
こんなことで勃起して、愛想をつかされてしまったろうか。きまりが悪くて、心細くなって、僕は慌てて顔を上げた。
兄貴は口隅を持ち上げて、僕を見下ろし、苦笑していた。それはそれで恥ずかしくて、僕は顎を引き、声を詰まらせた。
「もう、寝るよ」
早く眠って、早く忘れてしまおう。寝てる間に、きっと欲望も収まってくれるはずだ。
そう思って、大人しく息を潜めていると、兄貴が笑う音が聞こえてきた。そうして、僕の脇にあった手が、ゆっくりと動き出す。
「兄貴……?」
狭苦しい布団の中でもぞもぞと動く気配を感じて、僕は薄く目を開いた。暗さにも随分慣れて来たけれど、兄貴は僕の胸に顔を埋めていて、なにをしようとしているのかはわからない。
兄貴の手が僕の足の上を通過して、制服のズボンの上から、僕の股間を包み込んだ。痛みや違和感を感じさせない、軽やかな手つき。ふわりと重なる掌に包まれて、僕は身を竦ませた。
「あ……!」
ついさっき突き抜けていったものと同じものが、再び僕の体を渉っていった。背中に汗をかくほどに蒸れた暑さを感じていたのに、一気に肌が寒くなって、僕は思わず身じろいだ。
「なに、するんだよ」
あんまり驚いたせいか、僕の声は上ずった。重なってきた兄貴を押し上げてみたけれど、兄貴の手はそこに貼りついたままだった。
「抜いてやるよ」
熱っぽい、甘ったるい声だった。いや、僕がそう感じただけだったのかもしれない。
僕の胸が高鳴るのと同時に、兄貴に握られている僕の性器がキュンと竦んで、膨らんだ。兄貴は動じることもなく、そこを擦って、揉むように掌を押しあててくる。
「い、いいよ、しなくて」
「このままだと俺が寝づらいんだよ」
そう言われると、僕はなにも言えなくなった。一枚の布団にぐるぐる巻きにされて、ただでさえ息苦しい思いをしているというのに、これ以上迷惑をかけてしまうのは申し訳なさ過ぎる。
僕の手は布団の上にあったし、自分で抜こうにも、この状態では兄貴に負担がかかってしまう。
「声、出すなよ」
低い声で、兄貴は囁いた。膝を使って体を起こして、さわさわと撫でた手でベルトを外していく。
抵抗しようと思えばできなくもない、柔らかな手つきだった。だから余計に拒絶できなくて、かといって自分から頼むというのも恥ずかしくて、僕は大人しく従って、体を硬直させ、口を噤んでいた。