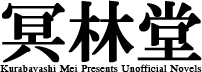本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
フタゴロール
[1] 困ったお兄ちゃん達
僕は、疲れていたんだと思う。仕方がない。ここ最近は、色んなことがありすぎた。
テレビに映し出される音楽番組を眺めながら、陽鞠は編み物をしている。兄貴は風呂に入っていて、ペンギンたちも、編み物の真似をしたり洗濯物を畳んだり、思い思いに過ごしている。
僕は両手を泡まみれにして、流しに立って皿を洗っていた。家事は楽だ。単純な作業を黙々とこなしていると、疲れた心が癒されていくような気がした。
水族館で買ってきたペンギン帽は、いつもの場所に飾られている。あれがうちに来て以来、僕らの生活は掻き回されっぱなしだ。
けれど、あのよくわからない宇宙生命体の言う通りにしなければ、陽鞠の時間は止まってしまう。
ピングドラムを手に入れなければ――。僕は静かに、重いため息を漏らした。
「あがったぞ」
湯気をたたせながら、兄貴が居間に戻ってきた。その足元では、すっかり湯だったペンギン1号が、御満悦で水滴を拭っていた。
兄貴は、ロングTシャツを頭からかぶり、ジャージの下を穿いて、首からタオルをかけた身軽な格好だった。細かく動いていた手を止めて、陽毬がにこやかに顔を上げる。
「お帰り冠ちゃん。湯加減はどうだった?」
「ちょうどよかったぜ。極楽極楽」
ごくらくごくらく、と、陽毬は兄貴の真似をした。引き続き、ご機嫌で運針していく陽毬の和やかな気配が、僕の背中にも伝わってきた。
「喉乾いたな」
僕は、スポンジでゴシゴシと皿を擦っていた。兄貴は冷蔵庫を漁って、ペンギン印の牛乳瓶を取り出した。
パッケージをむしると、兄貴が左に傾いてきて、僕の右側が温かくなった。腰に手を当て、ゴクゴクと一気にミルクを飲み干して、兄貴は口許を手で拭い、小さな声で囁いた。
「――なにか、進展あったか?」
テレビと編み物に夢中でいる陽鞠には、聞こえない声量だった。僕が、ちら、と後ろを盗み見てそれを確認すると、兄貴は僕の視界を妨げるように、顔を覗きこんできた。
あの日から僕らは、ペンギン帽の命じるままに、ピングドラムを探していた。唯一の手掛かりは、荻野目さんの妄想が綴られた日記だけ。
荻野目さんっていうのは櫻花御苑女子高の生徒で、僕らの担任である多蕗のストーカーだ。多蕗はそうとは知らずに仲良くしてるみたいだけど、危なっかしくて仕方がない。
「全然。今は、明日のパーティのことで頭がいっぱいなんじゃないかな」
兄貴の首からは、貼りなおしたばかりの絆創膏が見えていた。兄貴が、荻野目さんが投げ捨てたペンギン帽を泥まみれで取り返してきたのは、つい先日のことだ。
兄貴は全身傷だらけで、今だって、パジャマの下に包帯を隠している。陽鞠に怪しがられてはならない。ただでさえ、最近の僕らは不真面目で、陽鞠を心配させてしまっているのだ。
それもこれも、あのペンギン帽のせいだ。でも、ピングドラムを手に入れれば全てが終わる。
陽鞠の病気も治って、僕らはようやく、なにごともない平和な生活を送れるようになる、らしかった。
「気楽なもんだ」
兄貴は肩を竦めて、呆れたようにため息を漏らした。
最近の荻野目さんは、迷走気味だった。時籠ゆりさんという強敵が登場し、ピリピリしていた。
有名人であるゆりさんに、勝ち目なんてあるはずがない。けれど、荻野目さんはしきりに『運命』という言葉を振りかざして、多蕗と親しいゆりさんに対して、異常な敵対心を燃やしている。
兄貴は、荻野目さんのことを煩わしく思っているようだった。だけど、報われない恋に奔走する彼女の姿を見ていると、なんだか憐れに思えてくる。
僕は小さなため息を漏らし、むくれた顔をしている兄貴へと進言した。
「曲がりなりにもデートなんだから、邪魔しないであげようよ」
「あの女のことじゃない。お前のことだ」
兄貴の冷ややかな視線を感じて、僕は手を止めた。兄貴は睨むように目を尖らせて、僕のことを見下ろしていた。
「悠長に構えてる場合じゃないぞ。陽鞠の命がかかってるんだ」
僕は言葉を失って、何度か瞬きをしてしまった。兄貴は深刻な顔つきで、僕のことを威圧した。
ペンギン帽が無ければ、僕らはあの日に逆戻りだ。テレビの前で、陽毬は無邪気に平和を楽しんでいるけれど、微笑ましいと思うのと同時に、その平和がいつ途切れてしまうことへの恐怖を感じていた。
陽毬の体が冷え切って、柔らかい体から命が零れ落ちていく感覚を、僕はよく覚えている。あんな思いは、もう二度としたくない。
僕の体にあの時の感覚が甦ってきて、震えだしてしまいそうになるのをなんとか耐えた。兄貴の真剣な様子に気圧されて、僕は思わず息を呑んだ。
コップを落とさないように握りなおしながら、取り乱さないように深く息をついた。顔が引きつっていることはわかっていたから、僕は俯いて、グラスの飲み口をスポンジで縁どり始めた。
「わかってるよ」
「いいや、わかってない」
呟いた僕の言葉を、兄貴は即座に否定した。少しカチンと来たけれど、僕が言葉を挟む隙もなく、兄貴は顔を近づけてきて、続けて言った。
「あんな女にいつまでも付き合ってないで、手っ取り早く奪っちまえばいいんだよ」
兄貴は、あのペンギン帽と同じ台詞を吐いた。それがまた、僕を少しイライラさせた。
明日、荻野目さんは多蕗に誘われて、舞台を見に行くことになっている。デート、だと言えるかどうかは微妙なところだけど、本人が楽しみにしているところに水を差すのも悪い気がする。
ついてくるな、と厳重に言われていたから、この週末、僕の出番はない。僕は渋く眉を寄せて、キュッキュッ、とコップを磨いていった。
「できるわけないだろ、そんなこと」
無理やり奪おうなんてしたら、彼女のことだ、なにをしでかすかわからない。わかっているだろう、と、同意を求めたけれど、兄貴は否定的に僕を睨みつけていた。
「できないことないだろ。相手は女だ。実力でいえば、俺たちの方が力は上だ」
「あれは一応、荻野目さんのものなんだ。それを無理やり奪うなんて……」
「陽毬がどうなってもいいのかよ」
小さい声ではあったけれど、低い声で漏らす兄貴の言葉が、僕の心に突き刺さる。
そんなはずがない。でも、だけど――。
苛立ちが増していって、僕は水道の蛇口を捻った。
「そんなこと言ってないだろ」
「だったら」
「でも無理だよ。大体、どうやって奪えばいいって言うんだよ」
いつもよりも荒い手つきで、僕は食器を濯いでいった。口唇を尖らせて尋ねた僕に、兄貴が答えた。
「方法はいくらでもあるだろ。寝込みを襲ってみるとか、抵抗できないように縄でふんじばっちまうとか」
状況を想像しただけで、僕の額には冷や汗が浮かびあがった。そんな犯罪めいたことを口にできる兄貴が恐ろしくなって、僕は兄貴を凝視して、声を荒げた。
「なんてこと言うんだよ!? そんなことしたら……」
「デカい声出すなよ」
兄貴の腕が、僕の首に絡みついてきた。僕たちは顔を見合わせて、ゆっくりと、陽毬の様子を窺った。
聞こえやしなかったかと肝を冷やしたが、陽毬は依然、テレビに映し出されるガールズユニットの映像に夢中でいるようだった。僕は安心して胸を撫で下ろし、兄貴は僕の耳元に冷ややかに囁いた。
「気をつけろ。陽毬に聞かれたらどうするんだ?」
「ゴメン…。でも、兄貴が無茶なこというからだろ」
恐縮して、僕は眉を伏せた。けれど、全てを全て僕のせいにされるのも気分が悪い。
「荻野目さんは、色々と面倒くさいんだよ。なにを考えてるのかよくわからないし…」
「だから、あんな変態女に付き合ってないで、さっさと用件だけ済ませちまえばいいだろ」
シャワーの水が洗剤を流していって、排水溝に泡がたまっていく。牛乳の空き瓶を握ったまま、焦れったそうに僕を覗きこんでくる兄貴の口振りが腹立たしくて、僕はきりりと眉をいからせた。
「そんなに言うなら、兄貴がやればいいじゃないか」
僕がそう言うと、今まで強気でいた兄貴が面食らったような顔をした。その隙を突いて、僕は立て続けに畳みかけた。
「振り回されてる僕の気も知らないで、文句ばっかり言うなよ。必要な時にはいないくせに」
濯ぎ終わった皿を、水切り籠に積んでいく。恨めしげな僕の発言に兄貴は目を丸くして、またすぐに視線を尖らせた。
「こっちはこっちで、忙しいんだよ」
「なにが『忙しいん』だよ。どうせ女の子と遊んでるだけだろ」
「お前には関係ないだろ」
「陽毬のことそっちのけで兄貴がなにしてるのかなんて、興味ないね」
僕はやっぱり、疲れていたんだと思う。もともと女の子と接することになんて慣れてなかったし、中でも荻野目さんは、僕にとって理解不能だ。
この一週間で蓄積された疲労感が、兄貴への反発にリンクした。不思議なことに、遠慮も淀みもなく、兄貴への悪態はするすると僕の口から流れ出た。
「あーやだやだ。女ったらしの冠葉菌が伝染る」
兄貴の手を払い退けるように肩を竦めて、僕は厭味ったらしく言い放った。手を放した兄貴も、苛立っているようだった。二人を取り巻く不穏な気配は、もはや誤魔化しきれなくなっていた。
「あんな女に手こずってるくせに、偉そうな口叩くな」
「偉そうなのはどっちだよ」
「弟なんだから、兄貴の言うことは聞いておけ」
「兄貴面するなよ。生まれた時間なんて何時間かしか変わらないくせに」
「二人とも」
高い声に、僕らは竦み上がった。振り返ってみると、そこには腰に手を当てて眉を吊り上げた陽毬が、仁王様のように聳え立っていた。
「今何時だと思ってるの? おっきい声で喧嘩して」
どうやら、音楽番組はエンディングを迎えたらしい。居間の方からは平和なコマーシャルを彩るおかしなテーマソングが流れて来ている。
陽毬は頬を膨らませ、怒った顔をしていた。なんて可愛らしい、僕らの妹。けれど、一度彼女を怒らせてしまうと、ただでは済まない。
「喧嘩じゃないんだ、これは晶馬が」
「違うんだ陽毬、これは兄貴が」
「言い訳しない!」
可愛い瞳を尖らせて、陽毬はぴしゃりと言い放った。僕らは反論する言葉を失って、申し訳ない気持ちで、体を縮めていた。
「御夕飯も済んで、あとはもう寝るだけなのに。一日の最後に喧嘩だなんて、ホント困ったお兄ちゃん達なんだから」
僕らはもう何度も、兄弟で喧嘩はしない、と、陽毬に約束した。だけど、喧嘩をするなという方が無理な話で、僕らが陽毬との約束を破ることは何度もあった。
「サンちゃんも、そう思うでしょ?」
陽毬の足元で、ペンギン3号が大きく頷いていた。居たたまれない空気を感じ、僕たちの傍で殴り合っていたペンギンたちも、顔を見合わせ硬直している。
「ちゃんと、仲直りしてもらわなきゃ」
喧嘩をしたら、ちゃんと『仲直り』をすること。それが、仲の悪い兄貴たちに妹が敷いたルールだった。
かといって、男は一度対立したら、そう簡単には引き下がれない。僕と兄貴は顔を見合わせ、互いに気まずいものを感じていた。
「ほら、こっちこっち」
陽毬の柔らかな指が、僕らの腕を掴んだ。僕は、少しドキリとした。そんなことなどお構いなしに、陽毬は僕らを居間の方へと連れて行った。
そこでは3号がふすまを開けて待っていて、ドンッと背中を押してきた。並べてあった布団に倒れこんだ僕の上に、転んだ兄貴が落ちてきた。
「いッ、重い!」
「陽毬、なにするんだよ」
「問答無用!」
僕の悲鳴を兄貴が掻き消して、それを陽毬が打ち消した。痛みを堪え、仰向けで見上げてみると、どこから取り出してきたのか、ロープを持った陽毬が意味深な笑顔を浮かべていた。