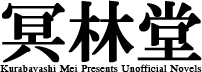本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
Baby Sun Rainy Moon
[3] 静かに、確かに降り注ぐ
流しっぱなしのテレビは、つまらないニュースを流していた。そのアナウンサーと顔を合わせるのは、初めてではない。いつもの顔を眺めながら、僕は、いつもの時間に腹が減っていないことを、不思議だとも思わなかった。僕はきっと、自分の家で、今までにないほど興奮していた。
リモコンを手にとって、ソファの背もたれに寄りかかりながら、彼が来るのを待っている。面倒な一日の最後を締めくくるには、あまりに愉快な出来事だ。
誰かが帰ってくるより先に、僕が彼を送ることになるだろう。変わらない日常のサイクルは、お陰でうまく利用できそうだ。
番組も終盤にさしかかり、今日一日のトピックを終えて、スポーツ情報に切り替わろうとした頃に、ようやく、彼が姿を現した。ジャージで膨らんだバッグを引きずって、遠慮がちにリビングへと入ってくる。
すかさず僕は、彼へとペットボトルを差し出した。コンビニで買ったばかりの、緑色のボトル。口の開いていないそれを見下ろして、彼は、温かい息を詰めた。
「いるなら、どうぞ」
短い付き合いだけれど、彼の性格は把握している。それが挑発だろうと、申し出だろうと、彼は、人の挑戦を受け流すことができないのだ。
だから僕は、先手に立った。自分に優位なポジションで、自分の優位を保ちながら。
案の定、彼は、す、と手を伸ばして、僕の手からペットボトルを受け取った。
ソファの真ん中から左にずれれば、あいた右に、彼がおずおずと腰掛ける。それがおかしくて、僕は、笑う口にペットボトルの口をあてた。
清涼飲料で喉を潤す僕の右半身が、彼の温もりを察知する。黙ったままの彼の緊張さえ、感じられるようだった。
「雨、朝まで止まないって」
目の前にあるテレビの画面は、天気予報に変わっていた。降水確率は、絶望的な数値を示している。
王様が、ああ、と、ぼんやりとした相槌を打つ。コンビニを出てから、ずっとこうだ。いつもの不遜さは鳴りを潜めて、落ち着かない様子で僕の調子を窺っている。
彼は、何かを言い出したがっている。それがなんなのか、僕は知っていた。
だけど、先手は僕のものだ。体育館のコートは彼の支配圏でも、ここは、僕の牙城なのだから。
「王様ってさ」
僕の隣で、彼が、びくりと震え上がる。らしくない反応だ。けれど、決して不快ではなかった。
「ホモなの?」
「はぁ?」
ペットボトルを掴んだまま、彼が、こちらを振り向いた。僕は肘をついたまま、その間抜け面を悠然と受け止めた。
僕が日向だったら、これまでの流れで、二、三発は叩かれていたかもしれない。けれど、君はそうしない。無防備で、隙だらけな貌を晒して、困ったように目を伏せる。
「…別に、そういうわけじゃない」
「説得力ないんですけど」
思わず、笑みを零してしまった。予想通りにいき過ぎるせいだ。
体育館の白いラインの内側でなら、自由自在にボールを操り、ゲームを翻弄する君なのに。欲しい気持ちを置き去りにするくらい、与えてくれているというのに。代わりに、僕の心を連れ去って。
「…なんでわかったんだよ」
苦々しげに眉を寄せて、王様は尋ねた。けれど、それに答える義務はない。だって今、君は、王様ではないのだから。
「気づいてないの?」
煽るように問い返すと、王様が顔を顰めた。もっともだろう。君を見つめている僕でなければ、気づかないのも無理はない。
「自覚した方がいいよ。あいつといる時、王様すごい、物欲しそうな顔してるから」
「――っ、誰が…ッ」
「でも、残念だったね。あいつ、ノーマルだよ」
たたみかけるようにそう言うと、王様の目が丸くなった。薄く開いた口唇が、同情を誘っていた。
君は必死に、希望を探しているんだろう。絶望から目を背け、努力と情熱が、現実を凌駕できると信じている。
その熱さが、腹立たしかった。その無邪気さが、苛立たしかった。
踏み躙ってやりたくなる。君が、僕を踏み躙っているのと同様に。
「男に惚れられてるなんて、一生気づかないかもね」
掌に頬を乗せて、僕の目は、もはや雑音を奏でる液晶ではなく、君に釘づけになっていた。その顔を見ていると、薄ら笑いすら浮かんでくる。
「日向に、教えておいてあげようか?」
「余計なことすんな」
やけにハッキリとした物言いで、王様はお命じになった。ム、と眉を顰めた僕に見向きもしないで、僕の与えたペットボトルを両手で握り締めている。
「知られなくたっていいんだよ」
諦めている、とでも言うのだろうか。確かに君は、『今』に満足しているのだろう。
今の関係が壊れることの、恐ろしさを知っている。だから君は、せめて君は、彼にボールを託すことで、満足しようとしているのだろう。
「ふぅん」
僕が洩らしたのは、我ながら無関心過ぎる相槌だった。崇高で高潔な理想を語るその口が、どれだけの苦渋を噛んでいるのか、僕はわかっているつもりだった。
だって、同じだけの苦味なら、僕が今まさに感じているところだったから。
「その割に、随分苦しそうだけど」
肩を揺らして、僕は笑った。ペットボトルに食いこんだ君の指が、震えているのを見つけたから。
「そんな思いして、なんか意味あんの? 好きだって伝えないで、伝わりもしないで…。じゃあ、そんな気持ち無意味じゃない?」
「お前に関係ねぇだろ」
王様は、気を悪くしたようだった。当然だ。そうなるように、わざと言葉を選んだのだ。
掠れた声で言い放った君の視線が、じろりと僕を睨みつける。たったそれだけに、こんなにも心をときめかせている僕は、どこかがおかしいのかもしれない。
「帰る」
不躾に言い放ち、王様が立ち上がった。その腕を、僕は逃さなかった。ぐ、と、指先を食いこませ、痛みを与えてしまっても構わなかった。
食い止められて、王様はぐらりと姿勢を揺るがした。なんとか立ってはいるけれど、体を傾けたまま、僕を凝視している。
「ホモのセッターって、気持ち悪いよね」
彼の腕を掴んだまま、ニヤついた口唇で、僕は言った。触っている指先から、君が僕の挑発でどれだけのショックを受けたのかを実感できた。
「…安心しろ。お前には二度とあげねぇ」
「他の人も、そうなんじゃない?」
腕を振り払われたから、それ以上、追いかけるのはやめておいた。僕がわざわざ捕まえなくても、続きを言えば、君は僕を捕まえにくるだろう。
「誰も打ってくれなくなるよ、あの時みたいに」
「テメェ――ッ」
期待通りの苦しさが、僕の胸を締めつけた。襟元を掴まれるのは、今日はこれで二回目だ。
本当に、予想通りの反応をしてくれる。それが、僕には嬉しかった。
「ねぇ、フェラしてよ」
あんまり嬉しかったから、僕はにやけた笑いを堪えられなかった。腰が浮くほど持ち上げてくる王様の右手を取ると、薄いシャツの上から、ゆっくりと指を添えていく。
「協力してあげるから、バレないように」
「バカじゃないのか、お前」
「したことないの?」
間髪入れずに尋ねると、答えに困って、息を詰まらせる。ああ、やっぱり、君のことは気に入らない。否定してくれれば、誤魔化してくれればよかったのに。
「あるんだ」
僕を捕らえる君の腕を捕まえて、僕は笑った。予め、第三ボタンまで外しておいて正解だった。きっと君は、また性懲りもなく、人の胸ぐらを掴んでくると思っていた。
「僕、してもらったことないんだよね。平気デショ、そのくらい。ああ、それとも…庶民のちんぽなんて、王様のお口にはあわないかな」
それでも君は、僕の心には触れてくれない。触らせてなどやらないのだ。だって、不公平だろう。
教えてなどやるものか。気づかない君が悪いんだ。
君が彼に焦がれているのと同じだけ、いや、もっと以前から、僕が君に焦がれていることに、気づかないなんて酷いじゃないか。
君に触れた指先から、火傷がどんどん広がっていく。これが恋なら、こんなものに溺れる人はバカだとしか言いようがない。
雨はざあざあと振り続けていて、冷たく家を冷やすのに、僕の心の炎だけは、決して冷ましてくれなかった。