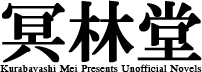本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
Baby Sun Rainy Moon
[2] 滴るシャワーの雨粒が
雨は嫌いだ。濡れるし、寒いし、冷たいし。うるさいし、静かだし――、だけど、今日に限っては、それは俺にとって好都合だった。
月島がまったく喋らないから、俺も喋る必要はなかった。道中、どこへ行くんだ、と聞いた俺に、月島はたった一言、『うちに帰るに決まってるデショ』、と、バカにしたように言い放った。
その言い方が気に入らなかったから、俺はやっぱり、月島と話すのを諦めた。そうして黙って歩く道のりは、少し、気が楽だった。
あのことについて、どう言おうか、どう誤魔化そうか考えていたけれど、今更、月島が騙されてくれるとは思えなかった。
こいつの性格の悪さは、短い付き合いでも十分理解していた。しょっぱなからああだったんだ、良く思おうという方が無理な話だ。
月島の家がどこにあるかなんて、俺は知らなかった。部活は同じだけれど、クラスは違うし、月島は自分のことをペラペラ話すような奴じゃない。
なのに、どうしてあのことを知っていたのだろう。俺は誰にも言わなかったし、日向にも、そして、当然他の誰にも気づかれないように、十分注意していたはずだったのに。
知らない道を、月島の傘を借りながら、少し遅れて歩いて行く。辺りを見回すのはバカみたいだったから、左右を見ない代わりに、俺は時々、月島の様子を窺った。
月島は、ただ前だけを見つめていた。わかったのは、月島の睫毛が思ったよりも長かったこと。
眼鏡に隠れて見えなかったから、こんなに近くにいることなんてなかったから、今まで知らなかった。別に、そんなこと知ったってなんにもならないのだけれど。
家に着いて、月島はまず、風呂場からタオルを取ってきた。無駄のない動きでスリッパを用意して、玄関に突っ立った俺に言った。
「靴下、脱いでくれる? 濡れたら面倒だから」
そりゃあ、雨に降られた俺の方が汚れてはいたけれど、月島の見下す視線が気に食わなかった。ぞんざいな手つきでタオルを受け取ると、月島は気に留めることもなく、俺に風呂場を案内した。
「風邪引いて、僕のせいにされても困るから」
有無を言わさぬ物言いだった。たとえ風邪を引いたとして、お前のせいにする気なんてない。けれど、そうしろと言うのなら、遠慮してやる義理もない。
「…お前、家族は?」
家に、人の気配はなかった。『ただいま』も言わなかったから、きっと、誰も居ないのだろうとは思った。
「出掛けてるよ」
ぶっきらぼうに、月島は答えた。俺が拭った雨で、濡れたタオルを受け取りながら。
家庭の事情に、深く首を突っ込むのも野暮な話だ。それなら気を遣わなくていいのだ、と、それだけを把握して、俺は、濡れたジャージを脱いだ。
シャワーを浴びて、体を暖めたら、家に連絡を入れなければ。夕飯がいるのかどうか、何時頃帰るのか、と、気にされていることだろう。
心配をかけていることは、申し訳ないと思っている。だけど俺には、もう少し、ここにいたい理由があった。
ついさっきまで、そんなことはまったく考えていなかったのだけれど。
ザァザァと、俺の上に温かい湯が降り注ぐ。髪に染みこんだそれが額に垂れてきて、項から背中へと落ちていく。
それが足許に広がるまでを感じきって、俺は、ゆっくりと目を開いた。
どうして、わかってしまったのだろう。いや、わからせてしまったことを悔やむべきだ。
本当は、誰にも知らせるべきじゃなかった。たとえ勘づかれたとしても、もっとうまく立ちまわるべきだった。
それなのに、何故あの時、誤魔化すことができなかったのだろう。そう考えて、見つけ出した結論を否定したくて、俺は濡れた頭を掻きむしった。
「――バカか、俺は」
他人の家で、初めて訪れた人の家で、しかも風呂場まで借りている分際で、よく言えたものだと思う。俺はきっと、誰かに知って欲しかったのだ。
一人で抱えているには、重すぎる感情に――、自分だけでは消化しきれないこの気持ちに、誰かに、気づいて欲しかったのだ。
キュ、と蛇口を捻って、俺はシャワーの湯を止めた。手に残ったお湯で顔をゴシゴシと擦って、燃え上がった感情を濯ごうとした。
ちゃんと、釘をさしておかなければ。多分月島なら、無闇やたらに言いふらすことなどないだろうけれど。
いや、もしかしたら、もっと残酷な方法で邪魔をしてくるかもしれない。何が邪魔だ、別に、叶う想いと思っていたわけでもないじゃないか。
これ以上一人でいると、混乱だけが錯綜してしまう。湯が水に変わる前に、俺は踵を返して、風呂場を出た。
バスマットに足をつけると、月島がタオルを用意していてくれたことに気づいた。薄くない、ふっくらとしたタオルが、家の格のようなものを感じさせた。
普段は素っ気ないくせに、むしろ、人を苛つかせるようなことしか言わないくせに。雨の中に置き去りにすることもなく、なにやかにやと気を回してくる。
もしかしたら、そんなに悪くない奴なのかもしれない。そんなことを思うのは、雨に打たれたせいだろうか。
頭からタオルを被って、髪を濡らした雫を拭う。濡れたジャージを着る気にならないから。バッグの中でぐしゃぐしゃになった制服を取り出した。
スラックスに足を通して、シャツのボタンを軽くとめる。濡れたタオルはどうしたらいいか、迷った俺は周りを見回した。
そこは整然としていて、急な来客にも決して驚いていない様子だ。洗濯機の隣のカゴに、さっきのタオルが投げられていた。俺はそれを真似するように、手に持つタオルを投げ入れた。
鏡には、髪の乱れた自分の姿が映っていた。自分が他人の家にいる事実は、タオルでも拭いようのない違和感を覚えさせる。
なんだか居心地が悪くて、俺は口唇を噛み締めた。脱衣所で短いメールを打ち終えると、俺は携帯をポケットに突っこんで、月島の姿を探して、風呂場を後にした。