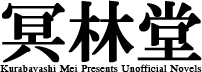本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
秘伝のレシピ
可能性というものは、万人に平等に与えられる。人は、無限の可能性を持っている。
そんなのは嘘っぱちだ。俺はそのことをよく知っている。台所に立つ晶馬の背中を眺めながら、俺は音の無いため息を漏らした。
晶馬は、俺の教えた秘伝のレシピを実演中だ。俺は、それが出来上がるのを待っている。
卵を解きほぐしていく軽快なリズムを聞いていると、残酷な現実に絶望した俺の心も癒されていくようだ。俺は瞳を閉じて、暫くの間、晶馬の奏でる音楽に耳を傾けていた。
「なぁ、まだー?」
もし晶馬が振り向いたなら、不満げな台詞とは裏腹に、幸福そうでいる俺の表情に気づけただろう。けれど、晶馬は気づかない。俺が煽れば煽るほど、晶馬は躍起なって、料理の手を動かした。
「うるさいな、黙って待ってろよ」
どんなに待たされても、文句なんてあるはずがない。晶馬の料理の腕は、誰でもない俺自身が保障している。毎日毎日、晶馬の料理を味わっている俺が言うんだから間違いない。
家の細かい作業は、俺がやるよりも晶馬がやるほうが断然効率的だ。料理にしたって、掃除にしたって、晶馬はまったく手を抜かず、むしろ少し細かすぎるほど気を遣っている。
俺のためじゃない。自分のためじゃない。病院で過ごすことの多い、俺たちのたった一人の妹が、快適に、楽しく、心地よく過ごせるようにだ。
「よし」
卵をとき終えて、晶馬は頷いた。長い菜ばしを握ると、器を持って、コンロへと足を踏み出した。
俺は瞼を持ち上げて、ちら、と視線を起こした。温められた鉄板からジュウジュウという音が響いて、甘い香りが俺の鼻にも届く。
今日の献立は、気合が入っている。夕飯の支度なんて、いつもはちゃっちゃと終わらせるのに、たっぷり時間をかけているようだ。
今度、久しぶりに帰ってくる陽鞠に食わせるためだ。晶馬のやることは、全て陽鞠のためだ。掃除も、洗濯も、料理も、全て――。
「やった、成功!」
俺は再び目を閉じたが、晶馬がなにをよろこんでいるのか、手に取るようにわかった。晶馬は、卵が焦げ付かないように、器用に菜ばしを操って、慎重にひっくり返しているのだ。
わかりやすい、単純な奴。晶馬のことを、俺はなんだって知っている。だって、生まれた時から一緒にいるんだから。
生まれてから、俺は何度も神様に感謝した。
神様、晶馬を生んでくれてありがとう。晶馬と俺を、兄弟にしてくれてありがとう。
神様、陽鞠を生んでくれてありがとう。陽鞠を、俺たちの妹にしてくれてありがとう。
そして、俺はそれと同じだけ――いやもっと、神様を恨んだ。
どうしてアンタは、俺たちを兄弟にしてくれやがったんだ。もっと別の形で出会っていたら、こんな気持ちは知らずに済んだのに。
どうして、陽鞠は俺たちの妹なんだろう。こんなに陽鞠を愛しているのに、それを苦しいと感じるだなんて。
絆なんて無ければ、俺はこんな切なさを知らずに済んだ。もっと本能に忠実に、欲望に正直に、生きていけた。
「なぁ、もう、腹ペコなんですけどー」
「もうちょっとだから、待ってろって」
ゆっくり立ち上がって、夕食の準備に勤しむ晶馬の背後に忍び寄る。その腰に手を添えて、肩に顎を乗せたら、卵焼きの甘い香りが俺たち二人を包み込んでくれるだろう。
晶馬はきっと驚いて、体をビクつかせるんだろう。なにするんだよ、と俺を詰って、突き放そうとするんだろう。
晶馬の手には、熱々のフライパンと、卵焼きのこびりついた菜ばしが握られている。晶馬の手が塞がっているのをいいことに、抱き締めて、鼻先を耳許に押し当てたら、晶馬はどんな顔をするだろう。
慌てふためく晶馬の頬に、口唇を押し当てたら。動揺し、体を緊張させる晶馬の腰を抱き締めて、なにかを言おうとする口唇を塞いでしまったら――。
「お待たせ、兄貴」
特製卵焼きを皿に盛り付けて、晶馬がそれを運んできた。ちゃぶ台は一気に華やかになって、温かい湯気が俺の頬を擽った。
「初めて作ったから、味の保障はできないからな」
口ではそう言っていたけれど、晶馬は自信ありげだった。そろいの茶碗に飯を盛ってきて、俺の真向かいに腰を下ろす。
「美味いに決まってるだろ。俺のとっておきのレシピを教えてやったんだから」
「ただの、テレビの受け売りだろ」
二人とも、腹を大分空かせている。出来上がった料理を前に、我慢する必要なんてない。
「いただきまーす」
声をそろえて、夕食が始まった。晶馬は、早速卵焼きに手をつける。俺は、なにから食い始めるか、ではなくて、つい先刻の儚い妄想の余韻に浸っていた。
晶馬に、俺の気持ちなんてわからない。俺がなにを考えているのかなんて、晶馬にはわからない。俺が、どれだけお前を愛していて、どれだけの絶望に踏みにじられているのかなんて――。
「――兄貴?」
いつもなら、俺が一番におかずに手をつける。食事を作ってくれるのが晶馬なら、それを味わい、ねぎらうのは俺の役目だからだ。
違和感が残らないうちに、俺は卵焼きに箸を伸ばした。ふわ、と柔らかい触感が箸の先から伝わって、口に運ぶと、蕩ける旨味が口腔に広がった。
「うん、美味い。これなら陽鞠にも安心して食わせられるな」
俺の笑顔に、晶馬は安心したようだった。一瞬、顔を嬉しそうに綻ばせて、箸を進めていく。
「うん、いける。陽鞠、よろこぶかなぁ」
「平気だって。うん、美味い」
俺は平然と、いつも通りを装った。晶馬の知らない俺を隠して、晶馬の知ってる俺を演じる。
生まれたときからそうしているから、特別苦労はなかった。それは確かに楽しい夕食で、確かに卵焼きは美味かったから、無理はない。
人生には、無限の可能性がある。それが嘘だってことを、俺は知っている。
だけど、晶馬には、陽鞠には、そんな悲しみを味わわせたくはない。当たり前の日常が、当たり前である喜びと苦しみは、俺だけが知っていればいい。
卵焼きの最後の一切れを頬張って、俺はそれをゆっくりと味わった。晶馬の作った料理は、それが誰のためであっても、俺の血となり、肉となって、俺の一部に変わっていく。
その喜びを、少しでも長く味わっていたい。その幸福に、少しでも長く浸っていたい。
そのためだったら、心も、体も、なにを犠牲にしたって構わない。たとえそれが、神様の強いた運命に逆らうことになろうとも。