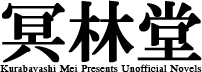本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
HONEY COME HONEY
[1] いつかと同じ曲がり角
先週降り続けていた雪も、晴れの日が続いたおかげで、随分少なくなっていた。屋根や地面、道路の隅にはちらちらと白さが残っているけれど、車通りの無い路面は、体を動かすにはお誂え向きだ。
久しぶりのロードワークで、吐く息は白かった。俺は道を選んで走り、低い屋根の向こうから差す斜めの夕日に目を細めた。
景色はすっかり冬色で、寒々しい景色を夕焼けが染めていく。北から吹く冷たい風は、夕食の香りを乗せている。
こんな景色があることを知ったのは、つい最近のことだった。去年の今頃なら、この時間俺はまだ、体育館に残って仲間と一緒に練習をしていた。
前からやってくる車に気づき、俺は脇の塀に寄り添った。だけど、走るスピードは緩めなかった。むしろ、俺は一層速度を上げて、住宅街を駆け抜けた。
冬の東北では、外で遊べるチャンスは少ない。晴れを喜ぶ子供達が、私道の中でサッカーをしている。
家と家との間にある狭いスペースで、器用にボールを奪い合っている。コートなんてなくたって、それが『遊び』なら、いくらだってやり方はある。学生用よりも少し小さなボールを追いかけて、声を出し合う彼らを、俺はあっという間に追い越した。
どれだけ走ったことだろう。行く宛がないわけじゃない。コースはいくらでもあったけれど、時期が時期だけに、走れる道は少なかった。
どこに行こうか、どれだけ走ろうか。俺は、あまり考えないようにしていた。走ること自体が目的で、行き先も時間も、俺にとってはどうでもいいことだった。
ロードワークも、もちろんバレーもできないで、雪の降る中、じっとしているなんて性に合わない。ひきこもりを強いられていた先週に比べれば、今日の日の、なんと清々しいことだろう。
たとえバレーができなくても、走っていれば、体を動かせば、なにも考えないでいられると思った。実際は、そんなにうまくはいかない。むしろ、止まっている時よりも余計に、頭が回転している気がする。
俺の気持ちも、思考も、あの日から同じところをぐるぐると回っている。季節は変わっていくというのに、俺は、全く前進できていない。
そんなはずがない、と確かめたくて、俺は、もっと早くと自分を急かした。苦しいのは呼吸じゃなくて、痛いのは体じゃなかった。苦しい、痛いと感じるより先に、俺は、夢中で足を動かしていた。
俺のバレーは、県大会のあの日、終わってしまった。毎日あんなに練習してたのに、終わりなんて、案外あっけないものだ。
同級生より少し早く、俺は引退した。『次の試合』のことなんて、考えられなかった。俺は三年生で、最高学年で、それに、あのチームの中に、俺のポジションなんてなかったから。
どうして、わかってくれないんだ。俺はきっと、いや、絶対に、他の誰よりも、チームのことを考えてたのに。
俺たちのしていたのは、『遊び』じゃない、『試合』なんだ。試合なら、勝たなければ意味が無い。俺の言うとおり、思ったとおりに動いていれば、絶対に勝てた、勝ち続けることができた。
文句しか言わない、反抗しかしない。そんな奴らと一緒にいたって、時間の無駄だ。早く卒業したい。卒業して、高校に入って、新しいチームに入れば、きっとまたバレーができる。
本当にできるのだろうか。また、同じことの繰り返しにはならないか。
サーブを決めて、レシーブで掬って、トスをあげた先に、誰もいなかったら…。随分走って、体は十分暖まっているはずなのに、足の裏から悪寒が突き抜け、膝からガクンと力が抜けた。
「ハッ、ハ……ック……!?」
その場で数歩よろめいて、近くの家の塀に手を伸ばす。体は驚き、全身がぞわついていた。パチパチと視界が弾けて、フラフラと世界が揺らぐ。
止まったらダメだ。筋肉が萎縮して、かえって負担がかかってしまう。
歩かなきゃ、前に、進まなきゃ──。俺は、震える膝を、ぎゅ、と掴むと、滴る唾液を腕で拭った。
そのままよろよろと、拙い足取りで歩き出す。あたりの家並みには見覚えがあった。知らないところに来たわけじゃない。俺は、少しだけ安心した。
だけど、どうしてここに来てしまったのだろう。数あるコースの中でも、ここは、できるだけ避けてきたはずだったのに。
ボヤけた頭ではうまく考えがまとまらず、俺はとりあえず、休む場所を探していた。
この先の角をまがれば、確か公園あったはずだ。遊具が少ない代わりに、屋根のあるベンチと、小さな自販機が置いてある。
記憶の通りの場所に、頭に描いたとおりの景色があった。車止めを避けて、中に入る。やはり雪は残っていたけれど、ところどころ地面がのぞいていた。
遠くで、孫を連れたお年寄りが犬の散歩をしていた。この寒い中、軽装の小学生が、ランドセルを放り出してキャッチボールをしている。
乾いた喉に無理やり唾を飲みこむと、俺は、雪の積もった東屋へと近づいた。屋根の下にある薄汚れた自販機は、相変わらず、低い声で唸っていた。
ポケットの中を漁って、小銭を取り出す。見上げたラインナップの中に、俺のお気に入りは見当たらなかった。
ここに来るのは久しぶりだから、俺のいないうちに、商品が変わってしまったらしい。俺が買い続けていれば、まだ残っていたかもしれないけれど。
いや、俺一人が通い続けたところで、あのまま置いていてくれたとは限らない。寂れた公園の、小さな自販機。その中に、俺の目を惹く一本があった。
派手な色をした、炭酸飲料だ。けばけばしいパッケージには、くねくねしたアルファベットが踊っている。
激しく動いたあとに、よくあんなものが飲めるな、と、俺はいつも感心していた。頭の中で、あの人の声がする。
『美味しいじゃん、わかりやすくて』
人口甘味料の甘ったるさが口の中に広がって、俺は軽く首を振ると、すぐ隣にあったスポーツドリンクのボタンを押した。
ガタガタと音を立てて、ペットボトルが落ちてくる。それを拾ってベンチに行くと、腰を下ろし、ボトルを一気に傾けた。
口の隅が汚れてしまっても、まるで気にしなかった。乾いた体は酸素以上に水分を求めていて、ボトルの半分が空になった頃、俺はようやく、深くため息を洩らした。
夕日は大分傾いてしまい、冷たい風が頬を掠める。濡れた口唇を舐め取ると、俺は、軽くなったペットボトルを、ぎゅ、と強く握りしめた。
最近またよく、あの人のことを思い出す。忘れようとしても、他のことで気を紛らわそうとしても、俺の無意識はいつの間にかあの人を探している。
あの人ならどうしただろう。主将と呼ばれて、みんなに親しまれて、勝利を繋いだあの人のボールと、俺のボールの何が違うんだ。
あの人は俺に、色んなことを教えてくれた。だけど、バレーだけは教えてくれなかった。
『人から教えてもらったって、つまんないでショ』
その通りだ、とは、今でも思う。
『やってみなよ、自分の力で。トビオちゃんの、やり方でさ』
だから俺は、やってみせた。俺の力で、俺のやり方で。
サーブもブロックも、最初は見よう見まねだった。それでも今では、周りに比べれば十分以上にうまく出来る。
練習に時間は惜しまなかった。誰よりも熱心に、真剣にやってきた。
それなのに、どうして──。指先がペットボトルに食い込んで、ペコ、と、歪な音が響く。
首を倒し、目を瞑って、静かにため息を洩らした時、向こうの方から声がした。
「すいませーん!」
顔を上げると、公園の奥の方で、小学生が大きく腕を振っていた。東屋を降りた先に、彼らのものであるらしい野球のボールがコロコロと転がってきた。
「投げてくださーい!」
俺はベンチから立ち上がると、ボールの方へと歩いて行った。それを掴んで顔を起こす。この距離を、わざわざ歩いて渡しに行くのも面倒だ。
拾い上げた軟球は、雪と土で汚れていた。冷たいボールを握り締めると、俺はそれを、思いっきり放り投げた。
灰色と赤色、紫色も少し混じった、夕暮れの空を背景に、野球ボールが風を切って綺麗な放物線を描く。山なりに投げたボールを受け止めて、子供たちが大きな声で、ありがとう、と言い、頭を下げた。
彼らに軽く手を振って、俺は、右手を見下ろした。投げたばかりのボールの感触が、まだ掌に残っていた。
心よりも正直に、体が違和感を訴えた。俺の知っているボールは、もっと大きくて、そして、もっと軽やかだった。
ピンと張られた布の中には空気が張り詰めていて、俺は、それを両手で掴み、弾力を確かめるのが好きだった。両手を押し返すように働く力、それを操っているのだという優越感に似た感情──。あの感覚をもう一度味わいたいという欲求が、俺の掌から全身へと、瞬く間に広がり始めた。
バレーがしたい。ボールに触って、ボールを操って、強すぎない、弱すぎない、絶妙なバランスを生み出したい。
この指で、この掌で、コート中を支配する。アスファルトではない体育館に、独特の足音を響かせて、汗を散らして、宙を跳んで、あの熱気の中に立っていたい。
「──クソ」
悔しさを言葉にしたら、もう止まらなかった。バレーをしたい欲求は、できないことへの苛立ちに変わり、何故できないのかを考えた時、もう、いてもたってもいられなかった。
俺は持っていたペットボトルをこじ開けると、中を一気に空にした。口の周りが汚れてしまって、胸はドキドキと高鳴った。
息を吐ききっても、それでもまだ、体がうるさくて仕方がないから、俺はペットボトルを握り締めて、ベコベコに凹ませた。
「ふざけんな、バカ野郎」
普段口にしないような罵詈雑言を吐き捨てて、ありったけの力で、俺は、ペットボトルを投げ捨てた。それは自販機の隣にあったくずかごの縁にあたって、遠くの方へと飛んでいった。
ふざけているのは誰かじゃなくて、バカなのも、誰かじゃなかった。だけど、俺は決してふざけてないし、バカでもないと思いたかった。
力任せに投げたせいで、コントロールが効かなかった。形が歪だったから、空気の抵抗もあったのかもしれない。
公園を汚して、誰かに怒られるだろうか。でももう、そんなことはどうでもいい。
別に、誰が見ているわけでもないし、わざわざ拾いに行くのも面倒だ。汚れた口許を袖で拭うと、俺はそのまま踵を返し、走りだそうとした。
「いーけないんだ」
顔を上げた瞬間、逃げだそうとした俺の体が、驚き、怯み、硬直した。目の前に現れたその人は、青葉城西の制服を着て、ペラペラの鞄を担いで、右手に、コーラのペットボトルを提げていた。
ごくりと息を呑む俺の脇を、ゆっくりと通り過ぎていく。そして、俺が捨てられなかったペットボトルを拾い上げると、笑みを浮かべて、その人は言った。
「ゴミはゴミ箱へ。貼り紙にもそう書いてあるでショ?」
空のペットボトルを指先で弄び、彼は、自販機の隣にあった汚れたポスターを指さした。俺の目は、彼にすっかり奪われていて、そこに書いてある文章を読むことすらできなかった。
寒さに悴んだ俺の口唇が、よく知る名前をぽろりとこぼす。
「及川、さん……!?」
俺は確かに、驚いていた。及川さんに会えたからじゃない。会いたいと、会えたらいいと思っていた、自分の気持ちに気づいたからだ。
「やっほ~トビオちゃん。久しぶりだねぇ」
及川さんが投げると、俺の時とは違って、ペットボトルはストンとゴミ箱に落ちていった。自分で飲んでいたコーラの空きボトルも捨ててしまって、身軽になった及川さんが、親しげに近づいてきた。
「ロードワーク? 精が出るね~。あれ、ちょっと見ない間に、また背ェ伸びたんじゃない?」
及川さんはそう言うと、無遠慮に、俺の顔を覗きこんできた。二年前に比べれば、成長したと自分でも思っている。
それでもまだ、及川さんには届かない。及川さんの顔が近くなって、俺は俯き、視線を逸らした。
「トビオちゃん、もう三年生だっけ。最近どう? みんな元気してる?」
先輩後輩の、久しぶりの再会。偶然の出来事だけれど、どこか胡散臭かった。
自分からこのコースを選んでおいて、胡散臭いもなにもない。俺は、きっと、及川さんに会いたかった。だからわざと、及川さんの家の近くまでやってきたんだ。
「ごめんね~、なかなかそっちにいけなくて。こっちも試合とか、練習で忙しくてさ~」
だけど、本当に会えるとは思わなかった。俺と違って及川さんには部活もあるし、こんな時間にここにいるのが不思議に思えた。
それ以上に、俺がここにいることを不審がられやしないかと、緊張する俺をよそに、及川さんはペラペラと喋り続けた。
「ホラ、来年俺ら三年だから、やんなきゃいけないこともいっぱいあってさ~。新しい一年生の面倒見なきゃなんないし」
何故俺がここにいるのか、及川さんは、あまり気にしていないようだった。俺は少し安心して、そして、なんだかとても、辛かった。
及川さんは、あのことを知らないのだろうか。いや、同じ県にいて、青城にいて、知らないはずがない。
知っているくせに、知らないフリをしているのだ。俺のことを気遣っているのだろうか。違う。及川さんはそんな優しい人ではないし、易しい人でもないはずだ。
「そういえばトビオちゃん、どこの高校にするかってもう決めた? 色んなとこから声かかってんでしょ~? 青城来れそう? それとも…」
「及川さん」
粘つく声で、俺は、及川さんの話を切った。及川さんの言葉の波が押し寄せてきて、息が、窮屈になっていた。
「……及川さんち、行ってもいいすか」
握りしめた俺の手は、小さく震えていた。寒いからではなかったし、悲しいからでもなかった。
俺は無性に、イラついていた。それを、及川さんはわかっているはずだった。
強張った顔を上げると、及川さんは笑っていた。いつものヘラヘラした笑みではなくて、どきりとするくらい淫靡な笑みが、睨み上げる俺のことを、これ以上なく挑発していた。