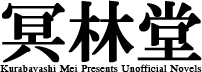本文ダブルクリックで縦書←→横書の切替ができます
烏の鳴かぬ日はあっても
[1] この手に秘める力はきっと
お前の力は、自分のためでなく、誰かのために使いなさい──、縁下力は、幼い頃から、そう言われて育ってきた。
人は成長する、成長した人は力を持つ。けれど、その力は自分のために揮ってはならない。自分ではない誰か、大切にしたい誰かのために、揮うべきだ。幼い縁下にも、その思想の美しさは十分以上に理解できた。
今は非力な自分であっても、いつかは強くなれるだろうか。体を鍛え、腕を磨き、蓄えた力を揮ってでも、共にいたい『誰か』に出会える日が、くるのだろうか。
期待は膨らむ一方で、いつしか、名前は誇りになった。しかし、馴染めば馴染むほど、縁下の名は重荷となって、彼自身を苦しめた。
けれど、今更否定しようがない。目を背けても、いくら拒んでも、そうなりなさい、と言われた言葉は、そうありたい、という目標となって、縁下の礎に刻みこまれてしまっていた。
体育館には、床を踏む足音がキュルキュルとよく響く。ボールを追いかけ、拾い、繋げる彼らの声が、練習への熱意を十分以上に伝えている。
「旭さん、もう一回!」
西谷は、東峰のスパイクを全力で追いかけていた。もう何十本もそうしているというのに、彼は音を上げるどころか、楽しげに次をねだっている。
「ダメだ、まだブレてる」
コートの反面では、澤村が厳しい声を響かせる。顎に滴る汗を拭い月島が悔しげに眉を寄せる。
「ほらそこ、また止まってんぞ! キビキビ動け!」
「あス!!」
澤村の隣で、烏養が檄を飛ばしていた。彼は、それぞれの練習を満遍なく周りながら、的確に鋭い指摘を刺しこんでいく。
青葉城西のキャプテンに指摘された通り、烏野の、特に、一年生の守備力の弱さは否めない。それを補強しなければ、全国大会への出場はおろか、激戦が予想される予選すらも危うくなる。
それぞれがそれぞれの強さを磨き、各々が各々の弱さを削ろうとしている。勝つためには、練習、練習、練習しかない。
周りが一心不乱に練習に励む中、日向と影山もまた、ひたむきに特訓に勤しんでいた。夢中になりすぎる余り、少々、暑苦しいとすらいえるほどに。
「アウトォオオ!」
「くっそぉおおお」
渾身の日向のスパイクは、残念ながらラインの中には収まらなかった。悔しがる日向とネットを挟んで、田中の誇らしげな笑い声が響いた。
「へっへっへー、甘いな日向」
「でも、あと少しだ」
茶々を入れる田中を窘めるように、菅原が労いを入れる。しかし、日向の悔しさが和らぐことはなかった。
日向が、音駒高校との一戦で拙いなりに体得した『コースの打ち分け』は、未だ完成には程遠い。けれど、相手校に『鉄壁』を謳う伊達工業がいる以上、今までのままでいるわけにはいかない。
「ちゃんと考えろ。いつまでもバカみてぇにフルスイングしてりゃいいってもんじゃねぇんだよ!」
憤りを散らすように、影山が日向を怒鳴りつけた。けれど、何度も繰り返される失敗に、焦れているのは影山だけではない。苦い表情で奥歯を噛み締める日向に、影山が続けて言い放った。
「ちゃんと見て、考えろ。ブロックの位置、ボールの位置、スパイクの角度、スピード、パワー…」
影山にガミガミと言われる内に、日向の中の悔しさは苛立ちに変わっていく。
「わかってるって、やってるって!」
「できてねぇから言ってんだよ! いいか、バッてきたら、シュビッてやって、ビュッ! だよ!!」
「だから、ガッてきたら、ビビッてやって、ドギュッ! だろ!?」
「まぁまぁ、とにかくさ」
コートの隅で始まった喧騒に、澤村が顔をあげるより先に、菅原が二人の間に割って入った。先輩に諌められて、影山がびくりと肩を竦めた。
「誰だって、いきなり完璧に合わせるのは無理だよ。慣れしかないって、烏養さんにも言われたろ」
日向と影山──。その連携の威力と効力なら、ふたりとも、既に十分自覚している。逸る気持ちと、個別の特訓に二人の先輩を付き合わせている罪悪感があいまって、彼らは、きゅ、と口唇を噛み締めた。
「もう一度行くぞ」
「いいから早く、トスくれ、トス!!」
ねだる日向を、うるせぇ、と一喝し、影山は、お願いします、と、声を出した。菅原にボールを放って、打たれたレシーブをトスの姿勢で待ち構える。
伊達工業のブロックは、あの東峰が苦戦したほどの『鉄壁』だ。それを打ち崩すには、烏野が誇る『最強の囮』に本来以上の力を発揮させねばならない。
トスの振り分け、スパイクの打ち分け。その双方が噛みあわなければ、鉄壁は剥がせない。
鉄壁を超えなければ、あの男とは戦えない。県内ベスト4に君臨する青葉城西、その主将、及川徹──。影山が誰よりも、戦いたい相手、乗り越えたい男。
わざとらしい彼の笑みが脳裏にチラついて、トスを送る影山の指に力がこもった。
「──ッ、やべ…ッ」
「え……!?」
空中で、日向は驚いた。ネットの前で跳び上がったその場所に、ボールが見つからなかったからだ。
振り上げた手を、どこに振り下ろせばいいのかわからず、日向は動揺した。田中の位置は掴めている、打ちたいコースも見えている。けれど、ボールがやってこない。
当然だ。山なりにやってくるはずのトスは、日向の思っていたよりもずっと速く、日向の横っ面に突き出されていたのだから。
「ぶふぉぁッ!!」
「日向!?」
「どうした、大丈夫か?」
日向の奇声を聞きつけて、練習の音が止んだ。盛大な音を奏でながら、まるでボールに殴られたように、日向が床に転がり落ちた。
影山の顔が引き攣って、彼はその場に硬直した。いち早く駆け寄ってきた澤村に抱き起こされ、日向は言った。
「ばいぼうぶべ…ゲハッ、ゴフッ」
大丈夫です、と言いたかったのだろう。しかし、途中で派手に咳きこんだ日向の様子は、『大丈夫』とは程遠い。それは、ボタボタと滴り落ちる鮮血からも明らかだった。
「おい、血ィ出てんじゃねぇか」
「え?」
西谷からの指摘に、日向は驚いた。顔を押さえていた掌を見下ろして、彼は忙しなく瞬きをした。
「なんだ、鼻血か。ビビらすなよ」
「派手に転んだなぁ」
「やばいなこれ、ティッシュあるか?」
周りが慌ただしく動き始める中、日向と影山は、まだ状況が理解できていないようだった。トスを送り損ねることなど影山にとっては珍しい失態であったし、日向は日向で、ボールを受けた顔面が痛いのか、血を流している鼻が痛むのか、自覚できていなかったのだ。
「いい顔になってるじゃん」
「笑っちゃ悪いよ、ツッキー」
日向を取り囲む月島と山口が、軽口を叩いた。血の色こそ鮮烈だけれど、けろりとした日向の表情が、大事でないことを示している。
「あー、こりゃ、あれだ。保険室いって、血ィ止めてもらってこい」
菅原の差し出したティッシュがどんどんと赤く染まっていく様を見て、烏養が指示を出した。ティッシュを鼻に詰めこみながら、日向は慌てて首を振った。
「平気っす。このくらい全然…」
「いいから立て。誰か連れて行ってやれ。おい、マネージャー…」
「ダメだぁあああ!!」
今度は、田中の大声が体育館中に響き渡った。目を血走らせ、顔を真っ赤にして、汚い唾を飛ばしながら、田中が続けて言い放つ。
「潔子さんと二人っきりなんて、許されるわけねぇだろうが!!」
「そうだぞ翔陽、百年早ェ!!」
田中の勢いに乗じるように、西谷が怒鳴り声を散らした。体育館の隅では、ジャージ姿の清水潔子が、レンズの奥で大きな瞳を瞬かせていた。
小気味の良い掛け声が響いていた体育館が、すっかり騒がしくなった。その間にも、日向が顔に押しつけていたティッシュにはジワジワと赤みが広がり、どんどん使い物にならなくなる。
「潔子さんの手をわずらわせるまでもありません。力、行ってこい!」
「え…、俺!?」
まさか自分に白羽の矢が飛んでくるとは思ってもおらず、別のコートにいた縁下が、拾おうとしたボールを取りこぼした。
縁下は、目立たない男だった。けれど今、彼が誰よりも部員たちの注目を集めていた。
天井を仰ぐ日向の隣で、菅原が、俺が行こうか、とでも言いたげな顔をしている。先輩にそんなことはさせられない。落としたボールを田中の方へと転がしながら、縁下は歩き出した。
「行ってきます。ほら、日向」
「悪ィな。頼む」
縁下を労うと、烏養が日向の腕を掴んで、縁下の方へと送り出す。日向は性懲りもなく平然を装いたがったが、烏養に押しやられて、意気消沈してしまった。
うう、と、言葉にならない声を洩らし、俯いてしまった日向の腕を引いて、縁下が苦笑する。
「顔あげてないと、シミついちゃうぞ」
前の見えない日向の代わりに、縁下が目の役をする。澤村の発声で、練習は何事もなかったかのように再開された。
オス、と声を出すと、少年たちはフロアに散らばっていった。ボールの弾む音、張りのある掛け声が響く中、ただ一人、影山だけが、体育館を去っていく二人の背中を睨みつけていた。